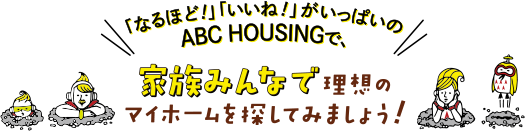土地を購入すると、土地の所有者に対して課税される税金があります。これは固定資産税と呼ばれており、市町村が主体となっている地方税の一つです。そこで今回は、土地にかかる税金である固定資産税について概要や計算方法、節税方法を解説します。是非参考にしてみてください!
土地にかかる主な税金の種類
土地にかかる主な税金は固定資産税

固定資産税とは、建物や土地等を対象として所有者が納税する地方税で税率は1.4%です。土地建物以外にも、機械や船舶など減価償却資産も固定資産税の対象となります。
固定資産税は1月1日時点の所有者に対して毎年課税され、1年分の税額を一括または4期程度に分けて納税しなければいけません。5~6月ごろにかけて、所有者宛に固定資産税の納税通知書が届くので、期限に間に合うよう納税しましょう。
しかし、固定資産税は地方税であるため、市町村が独自で納税時期などを定めていることがあります。固定資産税の納税方法や納期に関しての詳細は、固定資産を所有している市町村にあらかじめ確認しておきましょう。
都市計画税とは?
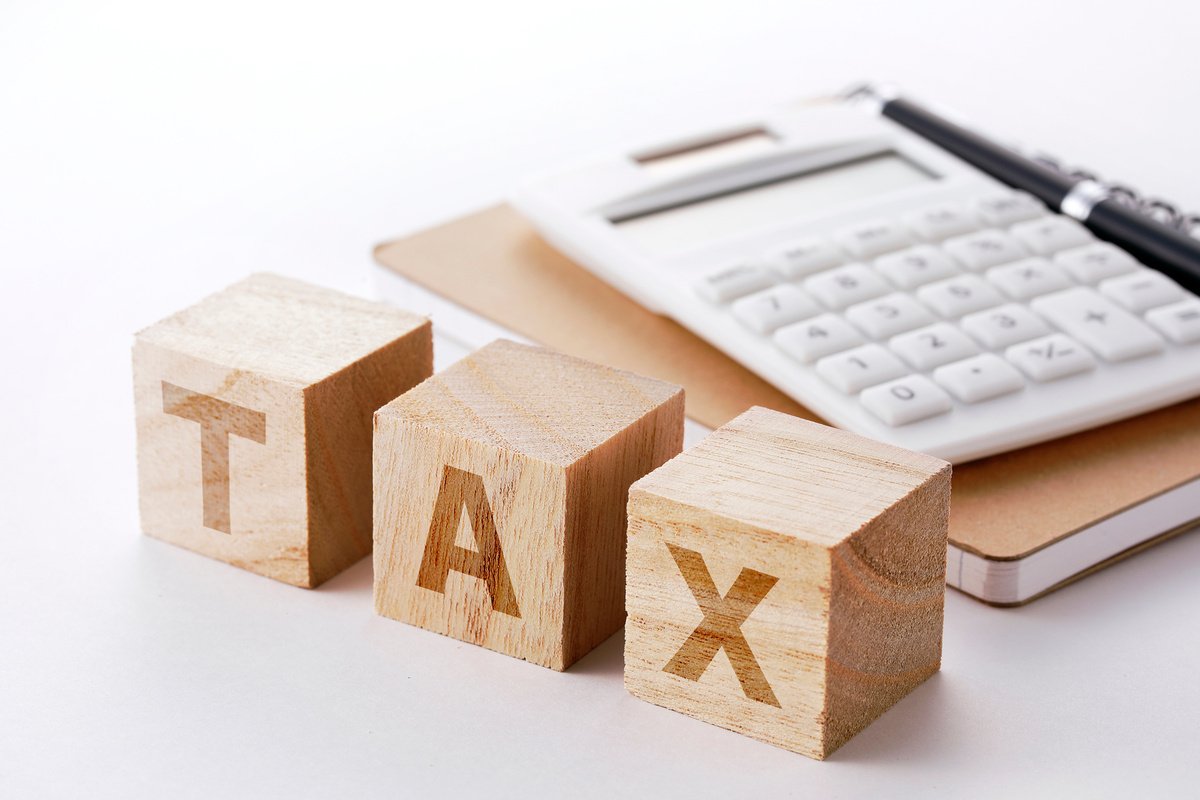
都市計画税も土地にかかる税金で、固定資産税と同時に納税します。都市計画税は用途地域内にある土地や家屋を対象とし、税率は一律0.3%です。用途地域外にある土地や家屋は、都市計画税として課税されないので覚えておきましょう。
このように、都市計画税はすべての所有者に課税されるのではなく、用途地域内の所有者が対象です。限定的な税金であるため、当記事では広く土地にかかる税金という意味で固定資産税を中心に解説していきます。
不動産取得税・登録免許税・印紙税の違い
不動産取得税、登録免許税、印紙税は、不動産を取得する際に発生する税金ですが、課税対象と納税先が異なります。
不動産取得税は、土地や建物を購入や贈与などで取得したという「事実」に対して、その不動産の所在する都道府県に納める地方税です。 不動産を取得した際に一度だけ課税されます。
登録免許税は、取得した不動産の所有権などを法務局に登記するという「手続き」に対して国に納める国税です。
印紙税は、不動産売買契約書などの法律で定められた「文書」の作成に対して課される国税で、収入印紙を貼付して納めます。
このように、課税されるタイミングや対象が「不動産の取得」「登記」「契約書」とそれぞれ異なるのが大きな違いです。
土地の固定資産税の仕組み
固定資産税は、土地や建物などを対象としている税金です。そこでここからは、固定資産税はどのような仕組みで成り立っているのか解説していきます。
固定資産税評価額の決まり方

固定資産税は、固定資産税評価額を基準に計算します。固定資産税評価額とは、土地や建物など固定資産の価値を基にして評価した額のことです。これは、固定資産税を取りまとめている市町村が決定しています。
また、固定資産税評価額は1年に1度郵送される、「固定資産税納税通知書」に同封されている課税明細書で確認できます。価格や評価額という欄に明記されている金額が、固定資産税評価額です。
課税標準額とは
固定資産税について用いられる用語に、前述した「固定資産税評価額」と「課税標準額」があります。いずれも、大きなイメージとしては固定資産の評価をしている額という意味です。
「課税標準額」とは、固定資産課税台帳に登録された価格を示しています。しかし、固定資産のなかでも住宅用地は課税標準の特例の対象となるなど、実際の土地の価格よりも課税標準額は少なくなる場合がほとんどです。
3年ごとの評価替えについて

固定資産税評価額は、土地や建物を購入したときの購入価格ではありません。市町村の固定資産評価員が固定資産評価基準に基づいて評価をし、市町村が決定します。また、決定された評価額は固定資産課税台帳に登録されますが、この評価額は3年ごとに評価替えされます。
ここで行われる評価替えは、簡単に言うと評価の見直しで3年ごとにある評価替えの結果、固定資産税の納税額が変わることがあります。また、評価替えをする年は基準年度と呼ばれ、そこから3年後にあたる次の基準年度までは評価替えは行われません。
次の基準年度までの3年間は建物の増築で固定資産が増えても、課税標準や納税額は変わらない期間となります。
土地の固定資産税の計算方法
ここからは固定資産税の計算方法について、実際の流れに沿って解説していきます。
①固定資産税評価額を調べる

初めに、固定資産税の計算基準となる固定資産税評価額を調べます。固定資産税評価額は、納税通知書に同封されている課税明細書で確認が可能です。また、市町村の担当窓口でも固定資産税評価証明書を発行してもらえます。
土地を所有している市町村が現在の居住地から離れている場合、郵送で対応してくれる場合もあります。事前に土地が所在している市町村へ問い合わせてみましょう。
おおむね時価の70%程度が目安
土地の固定資産税評価額を概算で知りたい場合、一般的に土地の時価の70%程度が目安となります。正式な計算を経た数字ではありませんが、概算で知りたい場合には周辺の売買価格を参考にして、固定資産税評価額の目安としてみてください。
固定資産税路線価から算出する方法も
固定資産税評価額を調べる方法として、固定資産税路線価から算出する方法もあります。固定資産税路線価に土地の面積をかけて求めた数字が、おおよその固定資産税評価額です。なお、固定資産税路線価とは、土地の形状などを基にして市町村ごとに決められています。
②土地の種類に応じて課税標準額を調べる

次に、土地の種類に応じて課税標準額を調べましょう。土地だけを所有している場合と住居が建っている土地の場合では、課税標準額が異なります。更地と宅地では課税標準額が異なる点もしっかりとおさえておきましょう。
また、課税標準額には免税点と呼ばれる基準金額が設けられています。土地の場合は30万円が免税点で、土地の課税標準額が30万円未満であれば固定資産税の対象となりません。
土地だけを所有している場合(更地など)

家屋が建築されていない土地を所有している場合は、固定資産税評価額の70%程度が課税標準額になります。市町村によって差がありますので、更地の場合にかかる課税標準額については、所有している土地を管轄する市町村窓口へ問い合わせてみましょう。
住居が建っている土地を所有している場合

住居が建っている土地を所有している場合は、条件に応じて固定資産税評価額が軽減される措置があります。評価額が低くなると課税対象が小さくなるので、それに合わせて固定資産税額も少なくなります。
- ●住宅やアパート等の敷地で200平方メートルまでの小規模宅地:固定資産税評価額×1/6
- ●住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以上の一般宅地:固定資産税評価額×1/3
いずれの場合も、建物本体の床面積の10倍が上限になっていますので注意しましょう。
200平方メートル以上の一般宅地では、その固定資産税評価額の全体を1/3として計算するわけではなく、200平方メートルまでは1/6とし、200平方メートルを超えた部分に対して1/3として計算する点についても注意しておきましょう。
③課税標準額と税率をかける

これまでに算出した課税標準額に、固定資産税の税率1.4%をかけることで固定資産税額がわかります。ただし、固定資産税の税率は市町村が独自に設定しているので注意しましょう。
一般的に固定資産税を1.4%に設定している市町村が多いため、当記事では固定資産税を1.4%として紹介しています。土地を所有している市町村の正確な固定資産税率に関しては、念のため事前に市町村窓口へ確認するようにしましょう。
土地の固定資産税を軽減・節約する方法

固定資産税は、一度土地や建物などを所有すると毎年発生する税金です。定期的な収入のある現役世代では負担と感じることも少ないですが、年金収入など老後資金で生活する世代になれば大きな負担になる可能性があります。
そこでここからは、少しでも固定資産税が節税できる方法について紹介します。以下に紹介する4つのポイントを理解し、老後のためにもしっかりと固定資産税を節約しましょう。
- 1.土地の情報に間違いがないか確認(登記簿上の情報や固定資産台帳の内容を再確認)
- 2.更地のままではなく居住用建物を建てる
- 3.分筆する
- 4.新築やリフォームに関する特例
書類と実際の土地に間違いがないか確認する

固定資産税の節約として、最初に現状の土地の情報に間違いがないか確認しておきましょう。土地の情報としてわかりやすいのは、登記簿上の面積の確認です。
しかし、固定資産税の計算基礎となる土地の情報は「実測値」という実際の面積を優先することになっています。そのため、登記簿上の面積と実測値に違いがある場合、市町村に申し出て実測値に変更してもらいましょう。
自身が購入した土地ではなく相続などで得た場合にはよくある間違いです。また、先祖代々引き継がれている土地の場合は、登記簿上の土地の形状が大きく変わっていることもあります。正しい面積となるよう、しっかりと確認しましょう。
固定資産台帳の縦覧制度を利用する
固定資産台帳には、固定資産税評価額が掲載されています。自分の土地の固定資産税評価額であるか確認するために、市町村ごとに設けられた縦覧期間内に台帳を見にいきましょう。
一般的には、固定資産税納付通知書が届く前後の期間で、縦覧期間を設けている市町村が多いようです。
更地のままにしない(居住用建物の建築)

家屋のない土地(更地)では、小規模宅地の特例が使えないため土地にかかる固定資産税も多くなってしまいます。土地の価格にもよりますが、更地でなく宅地として所有することで土地の固定資産税の軽減が可能です。
また、更地上に建てる建物は何でもよいわけではなく、居住用であることが前提です。人が居住しない小屋などは対象外となります。居住用の建物は所有者本人が住む必要はなく、賃貸アパートなどを建築して入居者を募る状態でも構いません。
空き家のまま放置するリスク

今は誰も住んでいなくても、もともと人が住んでいた建物がそのまま残っている土地は宅地とみなされます。誰も住んでいない家を解体し、更地にしてしまうと宅地の特例が使えません。しかし、誰も住んでいない空き家を放置することは、防犯上あるいは自然災害の被害などリスクが高いため、ペナルティの対象となってしまう可能性があります。
具体的には「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市町村から空き家認定をされてしまうと宅地に対する固定資産税の特例から除外されます。そのため、結果的に固定資産税が上がってしまいます。
遠方の実家を相続したなどの事情で空き家になっている場合、早めに売却や処分など検討することがおすすめです。
土地を分筆する
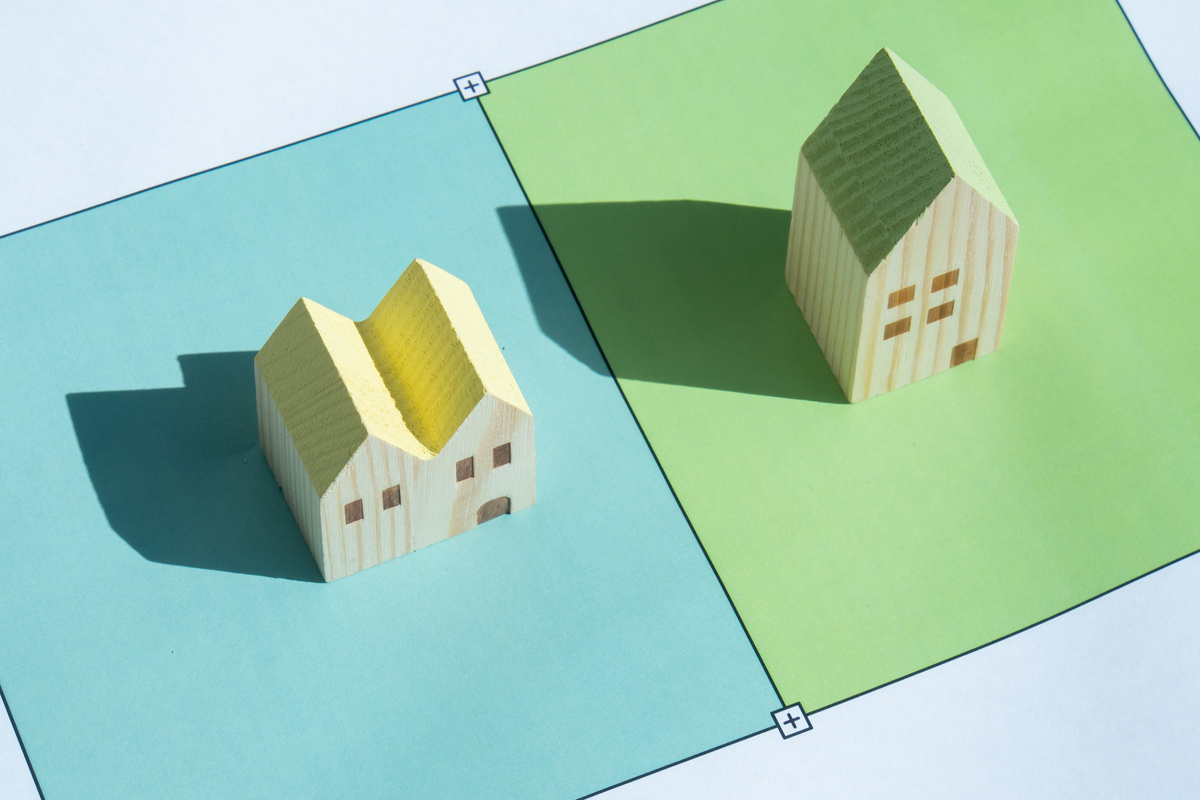
分筆とは一つの土地を分割することです。一つの土地のことを「一筆」と呼びますが、一筆を分けるため分筆と呼びます。分筆することで、実際にあまり使っていない利便性の低い土地は固定資産税評価額が低くなります。その結果、全体としての固定資産税の負担軽減につながります。
しかし、分筆には測量の依頼や測量後の司法書士による登記も必要です。時間や費用がかかることから、分筆をするかは熟慮したほうが良いでしょう。
新築やリフォームに関する軽減措置

新築やリフォームに関する軽減措置とは、土地とセットで納付すべき建物の固定資産税の特例を指します。土地と建物はセットで納税するため、建物の固定資産税の負担軽減もおさえておきたいポイントです。
そこでここからは、新築とリフォームの特例制度について紹介していきます。
新築・固定資産税の軽減措置

以下の要件を満たした新築住宅の場合、固定資産税が3年間にわたって(マンションの場合は5年間)1/2に減額されます。
ただし、2022年(令和4年)4月1日以降に建築される建物で、土砂災害警戒区域等の区域内に建てられる場合は軽減措置の対象外となるので注意しましょう。
- 2026年(令和8年)3月31日までに新築された住宅であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 店舗兼住宅などの併用住宅である場合、居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上であること
リフォーム・固定資産税の軽減措置
固定資産税の軽減措置の対象となるリフォームを実施した場合、それぞれ1年間にわたって適用されます。
| リフォームの内容 | 軽減される内容 |
|---|---|
| 耐震改修 | 税額×1/2 |
| バリアフリー改修 | 税額×1/3 |
| 省エネ改修 | 税額×1/3 |
| 長期優良住宅課改修 | 税額×2/3 |


住宅の大きさや設備に応じて変わる固定資産税。
モデルハウスを見学して、自分たちにあった大きさをイメージすることも、税金対策を考慮した家づくりには重要なステップ!
まずは、お近くのABCハウジングで気になったモデルハウスを見学して計画の第1歩を踏み出しましょう!
よくある質問(FAQ)

土地の固定資産税はいくらが相場?
固定資産税の相場は、土地の評価額や所在地によって大きく異なります。目安として、固定資産税評価額は時価の70%程度とされています。例えば、評価額が1,000万円の土地であれば、標準税率1.4%を掛けて、年間の固定資産税はおおよそ14万円になります。ただし、住宅用地の特例措置などにより、税額は軽減される場合があります。
固定資産税は年に何回支払うの?
固定資産税は、原則として年4回に分けて支払います。納税通知書は、毎年4月から6月頃に市区町村から送付され、一括払いも選択できますが、割引などはありません。納付時期や期限は自治体によって異なるため、送られてくる納税通知書を確認しましょう。
税金が高いと感じたときはどうすればいい?
まずは、市町村役場に問い合わせて、課税内容に誤りがないか、軽減措置が適用されているかなどを確認しましょう。新築住宅やリフォーム、住宅用地などには税金の軽減制度があります。それでも納得できない場合は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。
まとめ
土地を所有すると、毎年「固定資産税」や「都市計画税」が課税されます。税額は、市町村が3年ごとに見直す「固定資産税評価額」を基に計算され、通常、時価の70%程度が目安です。
固定資産税の節税には、更地に住宅を建てることで適用される軽減措置が最も効果的です。他にも、登記情報の確認や土地の分筆、新築・リフォームの特例を活用する方法があります。一方で、空き家を放置すると税負担が増える可能性があるため注意が必要です。
これらの税金の仕組みを正しく理解し、ご自身の状況に合った対策を講じることが、賢い土地所有の第一歩と言えるでしょう。




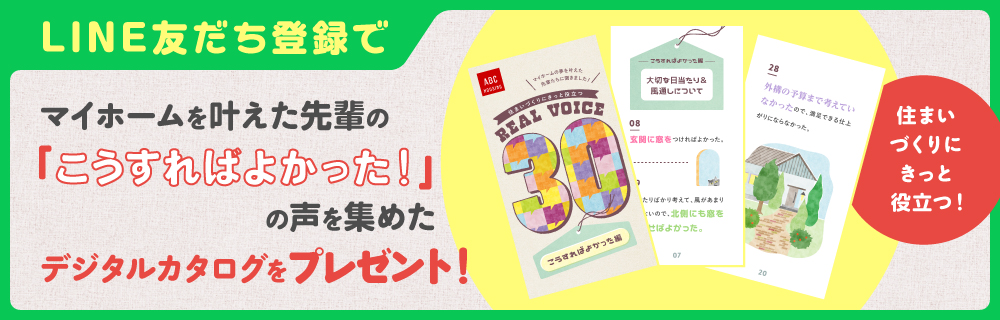
 前の記事
前の記事