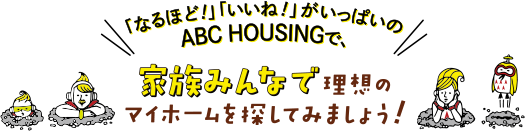「マイナス金利政策が解除されたの?」「住宅ローンにはどのような影響があるの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、マイナス金利政策の解除について
- ●マイナス金利が解除される背景
- ●住宅ローンの金利の決まり方
- ●マイナス金利の解除による住宅ローンへの影響
- ●金利が上昇することでの住宅ローン返済額への影響
- ●住宅ローンの金利が上昇した時の施策
を紹介します。
住宅ローンの金利は上昇する可能性がありますが、この記事では家計への負担を抑えるための対策も紹介します。正しい知識を身に付けることで、より前向きに住宅購入を検討できるようになるでしょう。
マイナス金利が解除される背景とは?

マイナス金利政策が解除されると、多くの家庭が住宅ローンへの影響を気にするのではないでしょうか。
ここでは、マイナス金利政策の概要と、解除された理由を解説します。
住宅ローンへの影響について理解するためにも、事前知識としてしっかり確認しておきましょう。
マイナス金利政策の概要
マイナス金利政策は、2016年に日本銀行が導入した手法で、金融機関が日本銀行に預ける一定額を超える当座預金に対してマイナス0.1%の金利を適用します。
この政策は、金融機関が余剰資金を日本銀行に預けるのではなく、企業や個人への貸し出しが活性化することを狙いとしています。
実際、マイナス金利政策の導入後、金融機関間での金利引き下げ競争が加速し、住宅ローンの金利も大幅に下がりました。
マイナス金利が解除された理由
マイナス金利政策が解除された背景には、日本の物価が安定するようになってきたことが挙げられます。
近年、物価上昇率が2%を超える事態が続いたものの、この上昇は主に原材料価格の高騰によるもので、賃金上昇が伴っていなかったため、真の物価安定とは言えませんでした。
しかし、仕事をする人が足りなくなってきたため、企業は賃金を上げて人を集めようとしています。その結果、2024年の春に行われた労働者と企業の交渉で、賃金の上昇率が過去33年間で最も高い水準になりました。
日本銀行はこれらの動向を受けて、経済が自然な形で物価安定の目標に向かっていると判断し、マイナス金利政策の解除を決定したのです。
住宅ローンの金利の決まり方とは
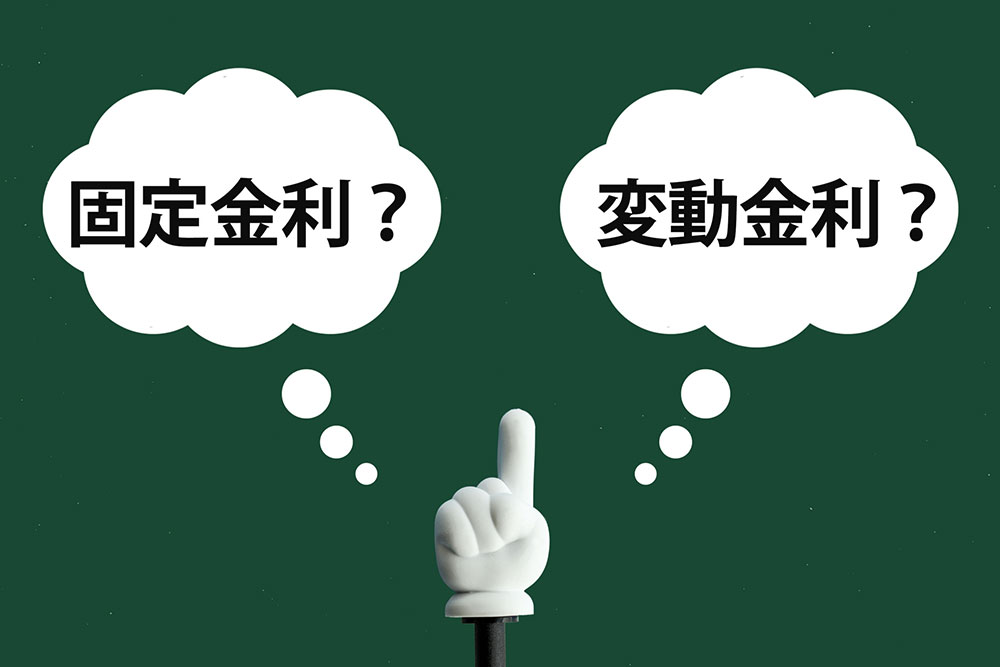
住宅ローンの金利は、家計の支出に大きな影響を与えますよね。
しかし、金利の決まり方をしっかりと理解しないと、ご自身にとって最適な住宅ローンを選ぶことができません。
ここでは、変動金利と固定金利の決まり方を解説します。
変動金利は、市場の金利動向に応じて定期的に金利が見直されるローンの金利です。
固定金利は、借入時に設定した期間同じ金利が適用されるローンの金利タイプです。
一般的に、将来の金利変動リスクを金融機関が負うため、そのリスク分を上乗せするために変動金利よりも固定金利が高くなります。
住宅ローンの金利の決まり方をしっかりと理解し、ご自身にとって最適な住宅ローンを選ぶための知識を身に付けましょう。
変動金利の決まり方
変動金利は「短期プライムレート」に影響されます。「短期プライムレート」とは、主要な大手銀行が大手企業向けに短期(1年以内)の期間で融資する際に設定する金利です。
日本では、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行といった大手銀行がこれを決定しています。
短期プライムレートは市場の動きによって毎月変わる可能性がありますが、2009年以降は1.475%という数値は変わっていません。(2024年4月現在)
これは、日本銀行が極めて低い政策金利を継続していることが理由として挙げられます。
日銀がマイナス金利政策の解除に伴う短期金利の上昇は 0.1%程度にとどまること、緩和的な金融環境が継続することを発言しています。
そのため、大幅に金利が上昇するとは考えづらいと言えるでしょう。
固定金利の決まり方
固定金利は「長期金利」を基準に設定されます。長期金利の代表的なものに「新発10年国債利回り」があります。
投資家が未来の金融環境を推測して市場での取引が行われるため、利回りは常に変動し、固定金利の設定にも影響を与えているのです。
固定金利の決定は、市場の現状だけではなく、将来の経済状況や金融政策の変更によっても左右されるため、住宅ローンを選ぶ際には長期的な視点を持つことが大切です。
マイナス金利の解除による住宅ローンへの影響

マイナス金利の解除は、住宅ローンを利用している多くの家庭の支出に影響を及ぼします。
ここでは、マイナス金利の解除が住宅ローンにどのような影響を与えるのかを解説します。住宅ローンを利用している方や住宅の購入を検討している方にとって、金利への影響を理解することは、最適な選択をするために必要な情報と言えるでしょう。
預金金利
日本銀行のマイナス金利政策の解除を受け、国内の主要な金融機関では預金金利の見直しの動きが加速しています。
例えば、三菱UFJ銀行、三井住友銀行といったメガバンクは、普通預金の金利を従来の年0.001%から0.02%へと20倍に引き上げることを決定しました。
しかし、この金利上昇とは別に、短期プライムレートについては、大手都市銀行が引き続き据え置く方針です。
このように、マイナス金利政策の決定は、個人の預金金利に大きく影響を与えることがわかります。
変動金利
先述したとおり、日本の多くの金融機関は、短期プライムレートに0.1%を加えたものを変動金利型住宅ローンの基準金利として採用しています。
現在、短期プライムレートは主要な金融機関によって据え置かれているため、変動金利がすぐに上がるとは考えづらいです。
変動金利の安定は、2009年以降、大幅な金融緩和政策が導入されて以来変わらない状況が続いており、住宅ローンの金利も基本的に安定しています。
金融機関は、基準金利が変わらない中で、利用者により有利な条件を提供するために優遇幅を拡大し、実質の借入金利を引き下げてきました。
その結果、住宅ローンの返済負担は大きく変わることがなく、利用者にとっては比較的安定した返済環境が維持されています。
また、多くの金融機関で「5年ルール」や「125%ルール」を設けているため、大幅な金利上昇が起こるとは考えづらいです。
「5年ルール」とは、半年ごとに見直しがされる変動金利でも、5年間は返済額が変わらないというルールのことです。
つまり、契約当初から金利が上昇したとしても、上昇した金利が適用されるのは6年目以降となります。
また「125%ルール」とは、金利上昇で毎月の返済額が増えることになった際に、増額する金額が前回の返済の125%を超えないようにするルールです。
これらのルールがあることで、住宅ローンの返済額が急激に増えることはないと言えるでしょう。
ネット銀行の変動金利
ネット銀行が提供する変動金利型の住宅ローンは、一般的に市場の短期プライムレートに直接連動せず、各ネット銀行が独自に設定しています。
その結果、ネット銀行の住宅ローンは通常、市場の金利変動よりも安定しており、利用者にとっては低金利と団体信用生命保険(団信)が充実している点が大きな魅力です。
しかし、これにはリスクも伴います。
日本銀行が金利を引き上げない状況であっても、他の要因によってネット銀行が基準金利を調整する可能性があります。
金利の上昇があっても、ネット銀行は新規顧客獲得や既存顧客の維持を優先する傾向にあるため、大幅な金利上昇は考えづらいでしょう。
固定金利
先述したとおり、固定金利は長期金利に連動しています。
日本銀行の政策変更によって長期金利が自由に動く様になりました。
しかし、長期金利が急激に上がらないように必要な措置をとることが見込まれています。
そのため、市場の動向や国際経済の変化によって長期金利にわずかな上昇が見られた場合でも、固定金利は大幅には上昇しないと考えられます。
この状況は、住宅ローンを検討している方にとって、家計への影響が少ないと言えるでしょう。
金利が上昇することでの住宅ローン返済額への影響

金利の上昇は、住宅ローンの返済計画に大きな影響を及ぼします。
ここでは、マイナス金利の解除後、金利が0.5%および1.0%上昇した場合に住宅ローンの返済額にどのような影響があるのかを紹介します。
マイナス金利の解除によって金利が変動するのは、変動金利です。
先述したとおり、固定金利は契約時に定めた期間は金利が変動しないためです。
住宅ローンを抱える全ての方々が、これからの金利変動に備えて賢く対処するために、どのような影響があるのかしっかりと理解しておきましょう。
0.5%上昇
金利が0.5%上昇すると、住宅ローンの返済額に影響が出ます。
具体的には、以下のように返済額に影響が出るでしょう。
【前提条件】
- ●借入金額:3,000万円
- ●返済期間:35年
- ●返済方法:元利均等返済
| 金利1.0% | 金利1.5% | |
|---|---|---|
| 月々の返済額 | 84,685円 | 91,855円 |
| 総返済額 | 35,567,804円 | 38,579,007円 |
0.5%と聞くと、返済額への影響は大きくないと考えるかもしれませんが、35年間の長期的な目線で考えると、総返済額が300万円以上増えることがわかります。
1.0%上昇
金利が1.0%上昇すると、当然ですが0.5%上昇したときよりも住宅ローンの返済額への影響が大きくなります。
具体的には、以下のように返済額に影響が出るでしょう。
【前提条件】
- ●借入金額:3,000万円
- ●返済期間:35年
- ●返済方法:元利均等返済
| 金利1.0% | 金利2.0% | |
|---|---|---|
| 月々の返済額 | 84,685円 | 99,378円 |
| 総返済額 | 35,567,804円 | 41,738,968円円 |
0.5%の金利上昇では総返済額が約300万円増えていましたが、金利が1.0%上昇すると、総返済額が500万円以上増えることがわかります。
このように、住宅ローンの金利が0.5%や1.0%上昇しただけで、総返済額が数百万円以上増えることは、家計にとって大きな負担になると言えるでしょう。
そのため、住宅ローンを検討する際には、固定金利や変動金利の特徴を踏まえつつ、資金計画を慎重に考える必要があります。
将来の金利を予測することは難しいため、必要に応じてお金のプロに相談しましょう。
住宅ローンの金利が上昇した時の施策
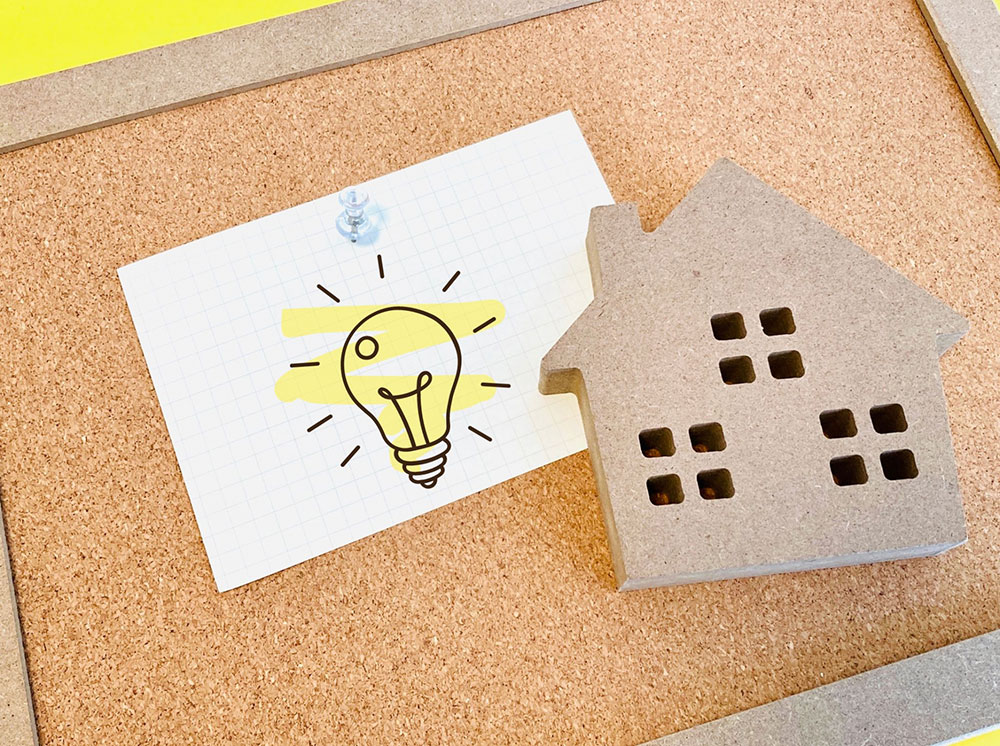
マイナス金利の解除に伴い、大幅な上昇はないものの、住宅ローンの金利が上昇する可能性は高いと言えます。
そのため、資金計画の見直しや対策を検討する必要があるでしょう。
ここでは、金利が上昇した際の具体的な施策を詳しく解説します。
それぞれのメリットとデメリットを理解しておくことで、ご自身にとっての最適な選択ができるようになるでしょう。
フラット35に借り換えをする
住宅ローンの金利が上昇した時に「フラット35」への借り換えを検討するのは賢明な選択です。
フラット35は、固定金利で最長35年間の住宅ローンを提供することで、金利の変動による影響を受けにくくするため、特に不安定な経済状況下での選択で有効です。
フラット35への借り換えを検討する際のポイントは、以下のとおりです。
- ●金利の比較:現在の住宅ローンとフラット35の金利を比較し、長期的に見てどちらが有利かを判断する
- ●総合的なコスト:借り換えに伴う手数料、違約金、その他のコストを詳細に調べ、総合的に判断する
- ●将来の計画:住宅ローンの残期間、将来の収入の見込み、家族構成の変化など、将来の経済状況を考慮して最適な選択をする
これらの要素を検討することで、借り換えが現在及び将来のニーズに合致するかを判断し、家計の安定と金利変動へのリスク軽減を図ることができます。
また、借り換えには利用できませんが、これから住宅ローンの利用を検討している方は、2024年2月にスタートした「【フラット35】子育てプラス」による金利の優遇もしっかりチェックしておきましょう。
子どもの人数による金利優遇
「【フラット35】子育てプラス」は、子育てをしている世帯や若年夫婦世帯に向けた住宅ローン金利優遇プログラムです。
具体的には、18歳未満の子どもがいる家庭や、借入時に40歳未満の夫婦(同性パートナーも含む)が対象となります。
この制度では、子どもの人数に応じて、一定期間住宅ローンの金利を引き下げることができ、家計に優しい条件が提供されます。
また「【フラット35】S」との組み合わせも可能なため、より幅広い選択肢を利用者が検討できるでしょう。
利用対象となるのは新規購入のみで、借り換えには利用できない点に注意は必要ですが、これにより、家計の支出を軽減しつつ、理想の住まいを手に入れることができるでしょう
金利の引き下げ幅が拡充
これまでの最大年▲0.5%の引き下げから、最大年▲1.0%へと倍増することで、利用者にとってさらに魅力的な選択肢となるでしょう。
さらに、新たにポイント制度が導入され、先述した子どもの人数や住宅の性能などによって金利が引き下げられることで、家計の支出軽減につながります。
これにより、購入を考えている家庭は、より低い返済額で住宅の購入ができるようになり、家計の負担が軽減されることは言うまでもありません。
詳しく知りたい方は、フラット35のホームページを確認してください。
補助金の活用
住宅ローンの金利が上昇した際、積極的に補助金の活用を検討することをおすすめします。
特に「子育てエコホーム支援事業」は、子育て世帯に焦点を当てた補助金で、2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、住宅の省エネ性能向上を支援する補助金制度です。
カーボンニュートラルとは、地球温暖化に対応し持続可能な社会をつくるため、温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにすることです。
新築やリフォームを検討している方々は、一定の条件を満たすことで最大100万円の補助金を受け取ることができるため、ご自身が条件を満たすかどうか確認しておきましょう。
「子育てエコホーム支援事業」を活用すれば、住宅のエネルギー効率を高めることができるだけではなく、住宅ローンの負担も軽減できます。
「子育てエコホーム支援事業」の利用を検討している方は、こちらのページから対象者や対象となる住宅についてご確認くださいね。
資産運用も併用する
金利上昇による住宅ローンの負担増加に備えて、資産運用を併用することも大切です。
株式や投資信託など、期待リターンが高い投資を通じて、収入の一部を増やすことができます。
ただし、投資にはリスクが伴うため、日々の生活を圧迫しないように、無理のない範囲で専門家と相談しながら運用計画を立てましょう。
繰り上げ返済を検討する
住宅ローンの金利が上昇した際は、繰り上げ返済を検討することも賢明な選択肢となります。
繰り上げ返済を行うことで、残債の期間を短縮し、支払う利息の総額を減らすことが可能です。
金利が上昇した際には、将来の利息負担が増加するため、早めに元本を減らすことが家計の負担を軽減することにつながります。
繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」があります。
子どもの教育費や日々の生活費から無理に繰り上げ返済をするのではなく、慎重に資金計画を立てたうえで、余裕資金で繰り上げ返済をしましょう。
期間短縮型
期間短縮型は、返済額を変えずに返済期間を短縮する方法です。
早くにローンを完済することで、老後の心理的な負担を軽減し、金銭的な自由を早く得られるという大きなメリットがあります。
期間短縮型は、返済のプレッシャーから早く解放されたいと考えている方に向いていると言えるでしょう。
返済額軽減型
返済額軽減型は、返済期間を変えずに毎月の返済額を減らす方法です。
特に、教育費などの出費が予想される際に、少しでも家計の負担を減らしたいと考える家庭に適しています。
返済額軽減型を選択することで、教育費のような支出に対応しやすくなります。
ただし、変動金利を選択した場合、金利の変動幅によっては想定したほどの節約が見込めない可能性もあるため、注意が必要です。
返済額軽減型は、返済期間を変えずに、毎月の出費を抑えたいと考える方におすすめの選択と言えるでしょう。
専門家に相談する
住宅ローンの選択や家の購入に際する資金の計画は、複雑で専門的な知識が求められる事が多いです。
そのため、資金計画を効果的に行うためには、専門家のアドバイスを得ることをおすすめします。
専門家からアドバイスをもらうことで、住宅ローンの選択や将来の資金計画について、家計のリスクを軽減する情報が得られるでしょう。
住宅の購入や住宅ローンの借り換えを考えているなら、一度ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。
不明点や心配事がある場合には、専門家から直接具体的なアドバイスを求めることで、より安心した決断ができるでしょう。
まとめ|住宅ローンの金利上昇に備えて理想の暮らしを実現しよう
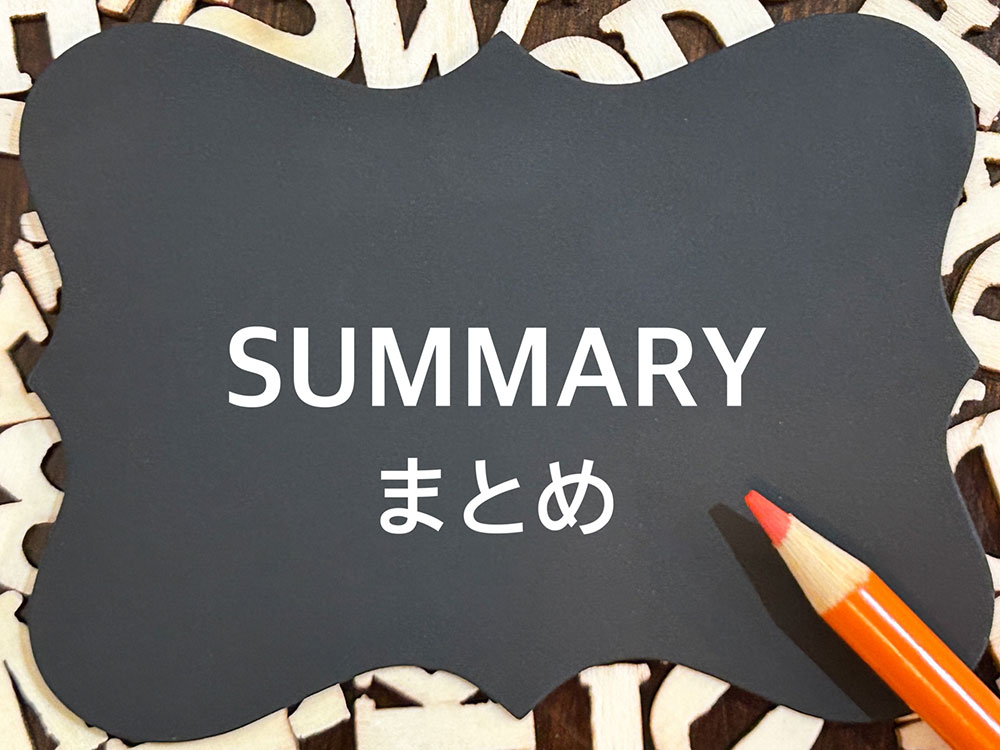
マイナス金利政策の解除により、住宅ローンの金利は変動金利及び固定金利のどちらも上昇する可能性がありますが、大幅に上昇する可能性は低いです。
しかし、金利が上昇すると総返済額が数百万円以上増えてしまう可能性があるため、フラット35への借り換えや補助金の活用、繰り上げ返済などの対策を理解しておきましょう。
また、これからの金利変動に備え、理想の生活を実現するためにも、専門家との相談を通じて、ご自身の状況に最適な選択を取りましょう。




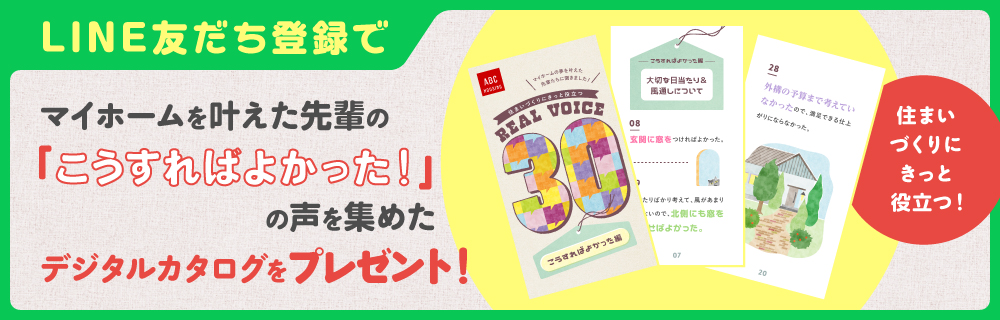
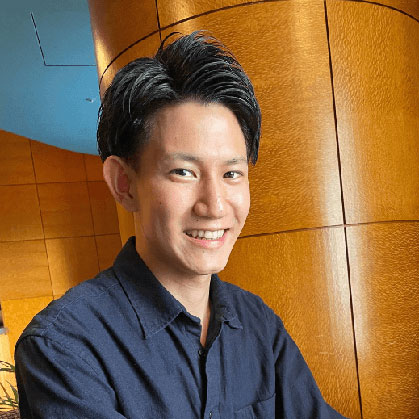
 前の記事
前の記事