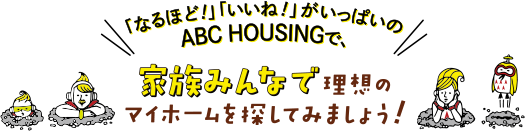注文住宅を建てる際、設計や間取りについては熟考しても、火災保険の検討は後回しになりがちです。万が一の際に十分な補償を受けるには、適切な火災保険に加入しておく必要があります。しかし、どのようにして火災保険を選べばよいかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、火災保険に関する保険料の相場や決まり方、保険選びの注意点などを解説します。家づくりを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
火災保険の必要性

総務省消防庁のデータによると、令和6年に発生した住宅火災は11,232件に上ります。内訳は一般住宅が7,291件、共同住宅が3,648件、併用住宅が293件となっています。総務省統計局のデータによると、令和3年の住宅総数に対して、一般住宅が52.7%、共同住宅が44.9%と割合に大きな差はありません。一般住宅(戸建て住宅)での火災件数が約2倍と、リスクの高さが浮き彫りになりました。
建物火災の主要な出火原因には、コンロや電気機器、たばこなどの身近なものが挙げられています。日常生活において、火災発生の危険性は常に存在しているといえるでしょう。
火災によって住宅を失った場合の経済的損失は計り知れません。火災保険による備えは、家族の暮らしと財産を守る重要な手段となります。
※参考:
・令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果
・令和6年(1月~12月)における火災の概要(概数)について|総務省消防庁
住宅購入時に加入する火災保険
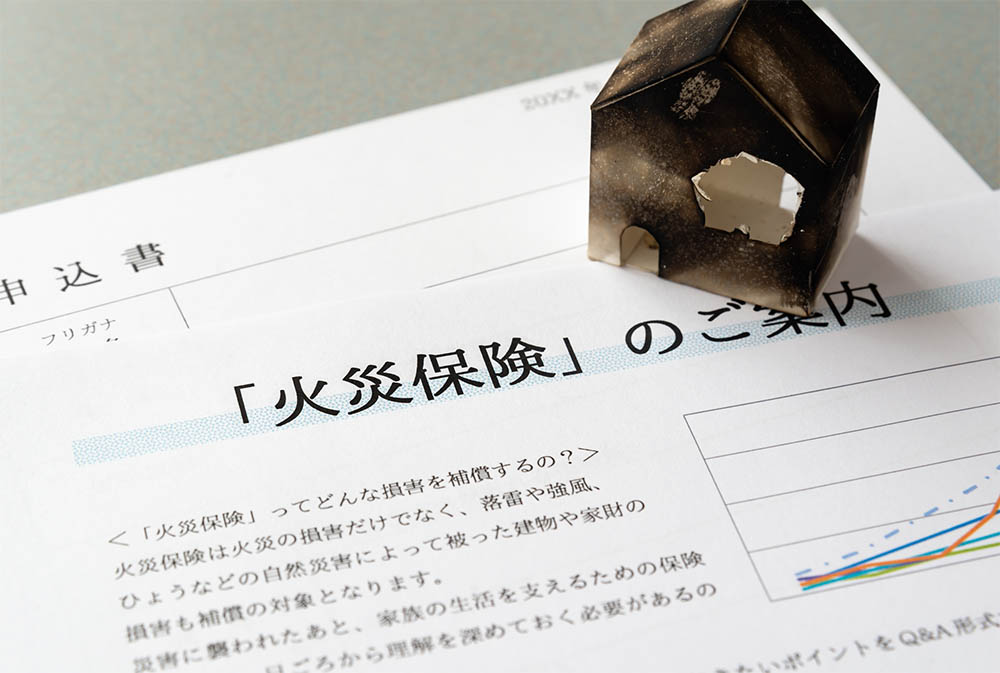
火災保険は、火災を含む幅広い損害に対応する保険商品です。商品によって差がありますが、補償範囲には風災・水災をはじめとする自然災害や、自動車の衝突のような偶発的事故、盗難や破壊行為といった人為的被害などが含まれます。
火災保険には、法的な加入義務はありません。ただし、住宅ローンを組む際は一般的に火災保険の加入が必須です。物件引渡し日を補償開始日とするためには、物件引渡し前に火災保険の契約手続きを完了させておく必要があります。
火災保険の対応範囲
火災保険は、火災による損害のみが補償対象と思われがちです。しかし、実際火災保険は以下のように多くの損害に対応しています。
- ●落雷
- ●風災
- ●雪災
- ●雹災
- ●水災
- ●水濡れ
- ●自動車の衝突や物体の落下・飛来による損害
- ●盗難や偶発的な破損などの人為的な損害
火災保険の保険対象は、主に「建物」と「家財」に分けられます。商品によって異なりますが、「建物のみ」「家財のみ」または「建物と家財の両方」を対象とする、3つのパターンから保険対象を選択可能です。
失火責任法について
火災保険に加入すべき理由として、近隣からの延焼リスクが挙げられます。失火責任法では、重大な過失に該当しない火災については「出火元の住宅所有者は、被害を受けた近隣住民に対する損害賠償義務を負わない」と定めています。つまり、隣家の火災によって自宅が損害を受けても、出火元に過失がなければ賠償を要求できません。
隣家からの延焼でも、自身で火災保険に加入していれば適切な補償を受けられますが、未加入の場合は一切の補償が得られない可能性があります。
注文住宅取得時の火災保険料

注文住宅を取得する際、火災保険料は建物の構造や築年数、延床面積、所在地などのさまざまな項目によって決まります。以下では、火災保険料の相場や保険料に影響を与える項目と、保険料の支払い方法について解説します。
火災保険料の相場
戸建て住宅における火災保険料の相場は、年間5万円程度が一般的な目安です。ただし、実際の保険料は個々の条件により大幅に変動します。条件次第では、想定している金額よりも高額になったり、反対に安く抑えられたりすることが少なくありません。以下では、保険料を決める各項目について解説します。
火災保険料が決まる項目
火災保険料は建物の構造や立地環境、契約内容によって決まります。火災保険料に影響を与える項目は以下のとおりです。
建物の構造
建物はT構造(耐火構造)とH構造(非耐火構造)に区分され、防火性能の違いによって火災保険料が設定されます。燃えにくいT構造のほうが保険料は割安です。
木造建築でも防火性能が高ければT構造となるように、建材だけではなく全体的な防火性能が火災保険料に影響を及ぼします。
築年数
築年数が経過した建物ほど、火災保険料は上昇する傾向にあります。建物が古くなるほど耐久性が低下し、自然災害による被害を受けやすくなるためです。近年は自然災害が発生しやすくなっており、築年数による火災保険料の差が拡大しています。
延床面積
建物の延床面積が広がるにつれて、火災保険料は高くなります。面積が大きいほど災害時の損害額が増大する傾向があり、保険金額を高額に設定する必要があるためです。
所在地
自然災害が発生しやすい地域にある建物は、火災保険料が高くなりがちです。例えば、台風の通り道となりやすい地域や豪雨による水害が頻発する地域では、他の地域と比べて火災保険料が高く設定されています。
補償内容
手厚い補償を求めるほど、火災保険料が高くなる傾向です。また、補償対象を建物のみとするか、家具や家電、衣類、食器などの生活用品を指す家財も含めるかによっても火災保険料は大きく変わります。
特約
基本補償では対応できない部分をカバーする内容を付加すると、火災保険料が上乗せされます。一例を挙げると、日常生活での事故に備える「個人賠償責任補償特約」を付加する方が多いです。
保険期間
火災保険の契約期間は、1~5年までの範囲で選択できます。短期契約の場合は火災保険料が割高です。長期契約のほうが、トータルで支払う火災保険料を抑えられます。
保険金額(補償限度額)
設定する保険金額が高いほど、火災保険料も高くなります。保険金額は建物の評価額を基準に決定されます。評価額とは、建物が全損した場合に同等の建物を再取得するのに必要な金額のことです。適正な保険金額を設定することで、無駄を抑えた火災保険料での加入が可能になります。
火災保険料の支払い方法
火災保険料の支払い方法には、月払い、年払い、一括払いなどの選択肢があります。一般的に、支払い期間が長期になるほど年間あたりの火災保険料は割安になる仕組みです。
ただし、火災保険料を一括払いすると、一時的とはいえ家計に負担がかかります。家計の状況を考慮して、適正な支払い方法を選択しましょう。
火災保険加入時のポイント

加入する火災保険を選ぶ際は、適切な補償内容の選択と、保険会社の比較検討が必要です。以下では、火災保険加入時に注意すべき3つのポイントについて解説します。
補償内容を精査する
火災保険の補償範囲を充実させるほど安心感は高まりますが、火災保険料の負担は重くなります。保険会社のプランには、加入中の他の保険と重複する内容や、不要な特約が含まれている場合があります。補償内容を精査して、無駄な補償を削りましょう。
ただし、火災保険料を抑えるために補償を削りすぎると、万が一の際に十分な対応を受けられないかもしれません。安全性と家計のバランスを考慮して、契約内容を検討しましょう。
複数の保険会社で見積もりを取る
保険会社を選ぶ際は、複数の保険会社で火災保険の見積もりを取得し、内容を比較することが重要です。
住宅購入時には、不動産会社が提携する保険会社を紹介されるケースが一般的ですが、不動産会社に任せきりにすると、内容を十分理解しないまま保険を契約してしまう恐れがあります。後になって補償不足や火災保険料の高さに気づいても、手遅れになりかねません。
複数社の見積もりを比較すると、各社の補償内容や料金体系の違いを把握でき、最適な保険を選択できます。最低でも3社程度は比較検討するとよいでしょう。
地震保険にも加入する
地震による建物や家財への被害は火災保険の補償対象外となるため、別途地震保険への加入が必要です。
地震活動が活発な日本では、地震保険は必須の備えといえます。また、地震保険は単独契約ができず、必ず火災保険とセットでの加入となる点に注意しましょう。
保険金額は火災保険金額の30~50%の範囲内で設定され、建物については5,000万円、家財については1,000万円が補償の上限額として定められています。
また、地震保険は地震保険料控除という制度があり、火災保険では適用されない所得控除の対象となっています。
※参考:地震保険制度の概要|財務省
あらゆる原因に備えた火災保険で家族と注文住宅を守ろう
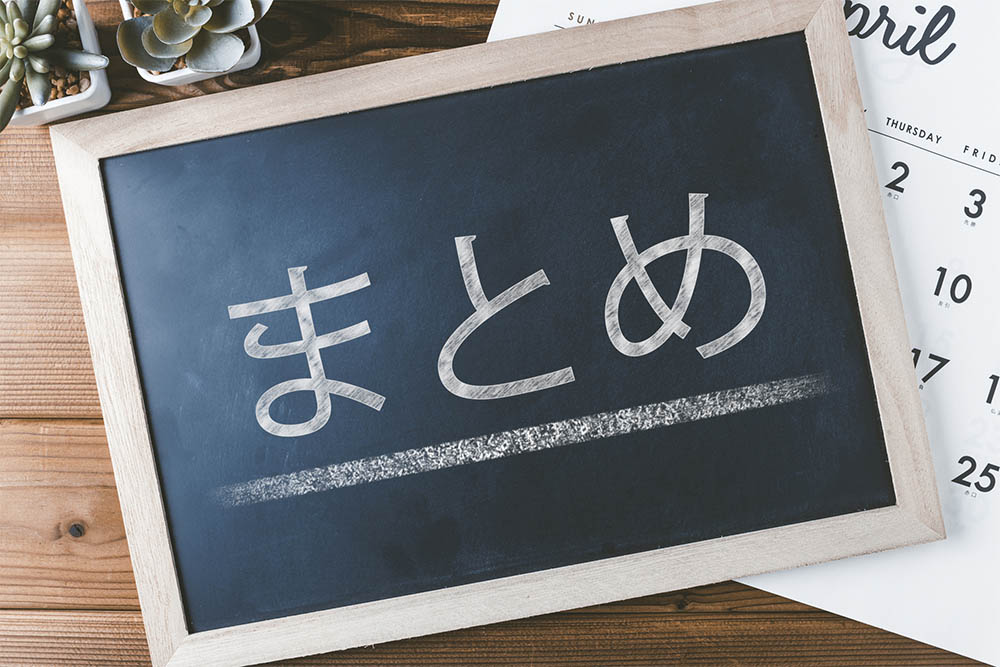
火災保険は、自然災害や人為的な事故による損害を補償する保険です。火災保険を契約する際は、建物の構造や立地環境などを考慮し、適切な補償を受けられるように検討しましょう。
ABCハウジングは、家族で楽しみながら理想の暮らしを思い描ける総合住宅展示場です。住まいづくりのプロフェッショナルに、火災保険をはじめとするさまざまなお悩みを相談いただけます。注文住宅をお考えの方は、ぜひお近くの展示場へお立ち寄りください。




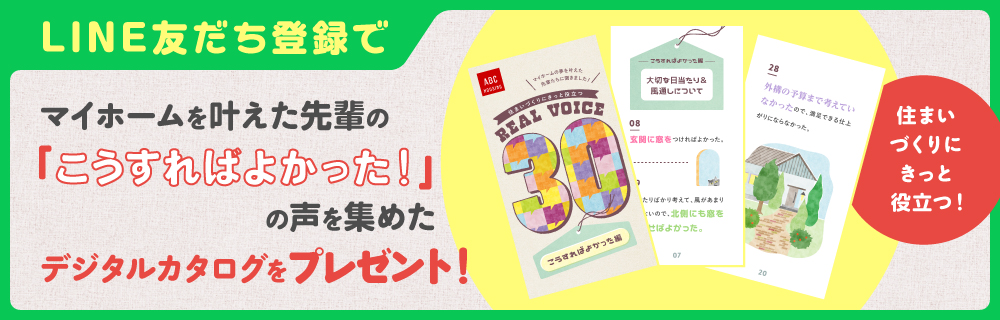
 前の記事
前の記事