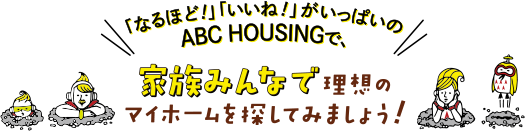人生の中でも大きな買い物であると言われる住宅購入。そのため、住宅ローン金利はしっかりと比較検討したいものです。そこで今回は、最新の住宅ローン事情について解説します。住宅ローン金利の相場から今後の見通しまで詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
住宅ローン金利の基本的な仕組みとは?変動と固定はどう違う?
まず、住宅ローン金利の基本的な仕組みについて解説します。住宅ローンの金利は大きく2つに分けられ、変動金利と固定金利があります。住宅ローン金利の概要や決まり方、それぞれの特徴についてわかりやすく紹介していくのでチェックしておきましょう。また、近年よく見かける固定と変動のミックス型についても解説します。
住宅ローンの金利はどう決まる?

住宅ローンの金利は金融機関によって異なります。借りる側から見ると金利はより低い方がよいですが、金利について調べてみるとおおむねどの金融機関も大きく違わず、ほぼ横並びです。
これは、住宅ローン金利は各金融機関が独自に設定しているものの、短期金利や長期金利を参考にしていることが理由となります。短期金利とは、日本銀行の金利政策をもとに決められているものです。長期金利は、短期金利や世の中の情勢(物価の変動や為替など)などをもとに決めます。
各金融機関が独自に金利を設定する際に、検討材料として主に用いているのが短期金利と長期金利であるため、そこまで大きな金利差がないのです。
固定金利の仕組みと特徴

固定金利は、住宅ローン金利が契約時から完済まで一律で変更がない仕組みです。返済期間中に金利変動がないため、借入時(住宅ローン契約時)に金利分も含めた総返済金額が把握できるという特徴があります。
借入時(契約時)から返済額や返済期間の変更がなければ、返済額は変動なく一律でよいため、返済計画が立てやすいというメリットがあります。しかし、一般的な固定金利は変動金利よりも金利が高いという点がデメリットとなるでしょう。
また、固定金利は10年物国債などで代表される長期金利を参考に決められます。長期金利については、先述の通り短期金利と世の中の情勢によって変動します。さらに、短期金利は日銀の政策金利も関係するため、固定金利が上がると変動金利も将来的には上がることになるでしょう。
変動金利の仕組みと特徴

一般的な変動金利は、返済期間中、半年ごとに金利が変動する仕組みです。金利見直しの時期は金融機関によって異なりますが、多くの金融機関は半年ごとに金利の見直しを行なっています。住宅ローン契約で変動金利を検討する場合には、事前に金利の見直し時期について確認しておくと安心です。
変動金利のメリットは、固定金利よりも金利が低いことです。また、金利は半年ごとに見直されますが返済額自体は5年間変わらないため、急に家計収支に大きな影響を与えることはありません。
変動金利のデメリットは、借入時(契約時)に今後の金利がわからないため、最終的な総返済額が固定金利よりも多くなっているかもしれないという点です。現状では変動金利の方が固定金利よりも金利は低く人気ですが、住宅ローンの返済期間は一般的に30年前後に及ぶため、長期的に考えると必ずしも変動金利がよいかどうかは断言できません。
したがって、変動金利のデメリットは、長期にわたる住宅ローンの返済期間において先が見えないという点と言えるでしょう。
変動と固定を組み合わせるミックス商品もある

固定金利と変動金利には、それぞれの特徴に基づいたメリットとデメリットがあります。この2つの金利タイプを取り混ぜた金利設定の商品も近年登場しています。金融機関によって商品の詳細や名称は異なりますが、「ミックス型」や「ミックスローン」と呼ばれているものが対象です。
金利をミックスした設定の商品では、一つの住宅ローン契約のうち所定の割合で変動金利と固定金利を選びます。例えば、5,000万円の住宅ローンのうち2,500万円を35年固定金利、残りを変動金利にすることが可能です。変動金利と固定金利だけでなく、期間の違う固定金利を組み合わせることもできます。ただし、フラット35は固定金利しかないため対象外です。
現在、ほとんどの金融機関でこのような金利をミックスする住宅ローン商品を取り扱っています。住宅ローンは返済期間が30年前後と長いため、長期的な視点で無理のない返済計画を立てましょう。
住宅ローンの現状とは?公的データから読み解く最新動向
住宅金融支援機構が公表している「住宅ローン利用者の実態」のうち、最新(2024年10月調査分)の内容をもとに、住宅ローン利用者の最新動向について紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
住宅ローン利用者のうち約77%が変動金利を選択

同調査によると、住宅ローン利用者のうち77.4%が変動金利を選択しています。2024年4月に実施された前回調査時は76.9%であったことから、最新の調査結果ではわずかに上昇していることがわかります。
変動金利の次に利用者が多いのは、固定期間選択型で13.5%という結果でした。前回調査時は15.1%であったことから、わずかに減少しています。なお、全期間固定型は9.0%となっており、前回調査時は8.0%であったことからこちらは微増しています。
変動金利を選んだ理由は「金利の低さ」と答えた人がもっとも多く、調査結果から、大半の借り手は低金利の魅力から変動型を選んでいる状況がわかります。しかし、最近は少しずつ、金利が変わらない全期間固定型を選ぶ人も増えてきました。
背景には、以前は変動金利が圧倒的に安かったのですが、最近少しずつ上がってきていることがあります。一方で、全期間固定型の金利も上がっていますが、将来の金利上昇リスクを避けたい人が選ぶ傾向にあります。
ただし、全体的には、まだ変動金利を選ぶ人が多い状況に変わりありません。
今後の住宅ローン金利は上昇していくと考える人が62%以上

同調査によると、今後の住宅ローン金利は現状よりも上昇していくだろうと考える人が62.9%となっています。現状とほとんど変わらないと答えた人が26.6%ほどで、上昇すると答えた人と合わせると90%近くの人が現状と変わらないまたは上昇するという回答でした。少なくとも、今後住宅ローン金利が下がると考える人は2.5%程度とかなり少ないことがわかります。
あくまで将来的な話ですが、新築戸建を検討している場合には、少しでも早く動いておくことで住宅ローンの金利上昇による影響を受けずに済むかもしれません。
変動金利と固定金利の金利リスクは約半数が理解していると回答

変動金利と固定金利には、それぞれメリットとデメリットがあります。特にデメリットにあたる金利リスクに関しては、契約前に把握しておくことが望ましいでしょう。同調査では、金利リスクについては約半数の人が「十分に理解している」「ほぼ理解している」と回答しています。
変動金利では、適用金利の見直しに関するルールを理解しているのは約55%でした。
今後の住宅ローンはどうなる?金利見通しの予測について解説
ここからは、住宅ローン金利の仕組みや最新の住宅ローン利用者の動向などをもとに、住宅ローン金利の今後の動向について予測していきます。
住宅ローン全体の予測

当面の間は、変動金利の低金利は継続するものと考えられます。特に、対面型の銀行だけでなくインターネット専業銀行では変動金利の低さはまだ続くでしょう。
一方、固定金利は日銀の方針として少しずつ金利を上げていくのではないかと推察されます。とはいえ、変動金利の低金利も長期間続くとは限らず、ライフプラン上は固定金利を選ぶ方がキャッシュフローが安定しやすいことに変わりはありません。
長期固定金利について

長期固定金利は若干の上昇局面にあるものの、いまだ1%台を推移しています。ただし、長期金利は今後も少しずつ上昇していくことでしょう。
先述したように、固定金利は短期金利と景気動向など世の中のお金の流れがポイントとなります。なかでも、景気動向で考えるといまだに先行きが不透明な部分が大きく、日銀が長期金利を上昇させつつあるため、住宅ローンにおける固定金利も上昇していくのではないかと考えられます。
変動金利について

冒頭でも触れましたが、現在の住宅ローン金利で選ばれているのは変動金利です。つまり、金融機関の売れ筋商品は変動金利であることがわかります。変動金利に関して、金融機関同士の競争が激化していることもあり、変動金利が大幅に上昇することは考えにくい状況です。ただし、日銀の政策金利の動きによっては、一斉に引き上げが実施されることもありえるでしょう。
変動金利は短期金利をもとに決められているため、原則的には固定金利の上昇が先に実施されてそのあとに変動金利の見直しが行われます。そのため、住宅ローン金利の引き上げに関しては、まず固定金利で次に変動金利という順番が一般的ではないかという考えです。
世の中の動向も踏まえて総合的に判断されますが、当面は変動金利の大幅な上昇はないのではないかと推察されます。
ライフスタイルに合わせてより最適な住宅ローンを選ぶには
実際に住宅ローンを選ぶ際に、より最適な商品を選ぶためのポイントについて紹介します。
家族のイベントを把握しお金の流れを知ろう

住宅ローンの返済期間で多いのが、30年前後の期間です。仮に返済期間を30年とすると、家を購入した時に生まれたばかりの子どもが、ローン完済時には30歳になっています。場合によっては子どもだけでなく孫も増えているかもしれません。それほど長い返済期間ですので、期間中にさまざまなライフイベントが発生します。
住宅ローン名義人の就職や転職、定年退職など、収入の増減に直結する出来事もあるかもしれません。子どもがいる場合には、教育資金の出費が続く期間と住宅ローン返済期間が重複することも考えられます。このように、暮らしの中での出費は一つではなく、複数が重複していることがほとんどです。
これらのことから、住宅ローンを契約する際には、今後のライフイベントに関する出費をあらかじめ把握しておくことをおすすめします。その上で、住宅ローン返済も含めた家計全体のお金の流れを確認し、無理のない返済計画のもとで住宅ローン契約をしましょう。
借入先を比較検討しよう

実際に住宅ローンの借り入れをする金融機関を調べて比較検討を行うと、自分に合った金融機関を見つけられます。できれば複数検討し、より自身にとってメリットのある金融機関を見つけましょう。
金融機関を選ぶポイントは人によって異なります。給与振込口座を保有している銀行を選ぶ場合や、購入しようとする住宅メーカーの担当者から勧められることもあります。
より金利が低い金融機関を選ぶことも大切ですが、30年にも及ぶ住宅ローンを契約する金融機関とは長い付き合いになるため、住宅ローン以外のメリットもある金融機関を見つけられるとよいでしょう。たとえば、ATM手数料が毎月複数回無料になるサービスや、金融機関のグループ企業で優待サービスを受けられる金融機関はメリットになります。
住宅ローン金利相場・まとめ
住宅ローン金利は、今後少しずつ上昇していくものと考えられます。金利が上昇する順番は固定金利が先で、そのあとしばらくして変動金利が上昇するものと推察されます。ただし、急激で大幅な金利上昇は固定金利も変動金利もないと言えるでしょう。先に固定金利がゆるやかに金利上昇し、少し遅れて変動金利も上昇という形だと予想されます。
まず今できることは、最新情報をもとに自身にとって最適な住宅ローンを選ぶことです。万が一大きな金利上昇があった場合でも、金融機関と連携し柔軟に対応していきましょう。




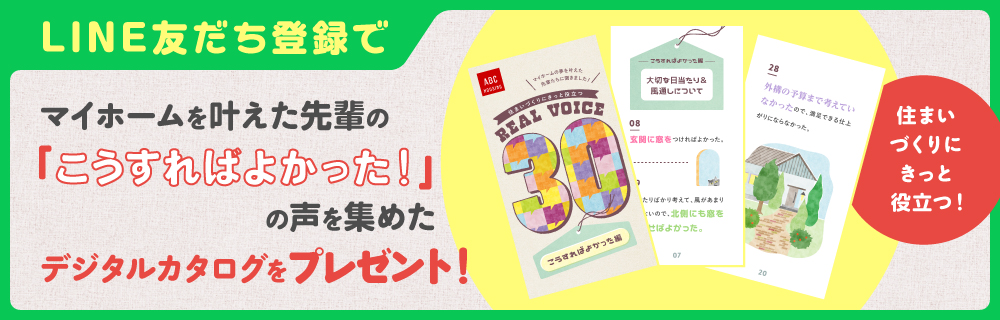
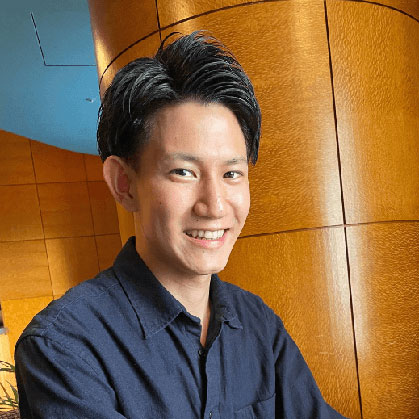
 前の記事
前の記事