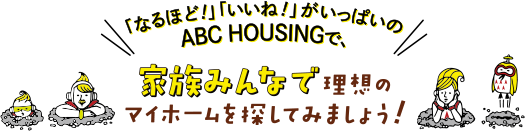「注文住宅の固定資産税を安くする方法は?」「固定資産税の計算方法は?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、注文住宅の固定資産税を安くする方法についてご紹介します。
そもそも固定資産税がかからない『免税点』とは?

必ずしも固定資産税が発生するとは限りません。実は、一定の条件を満たす場合には、そもそも課税されないケースがあるのです。
ここでは、固定資産税がかからない「免税点」とは何か、その仕組みや注意点についてわかりやすく解説します。
「免税点」とは? なぜ存在するの?
固定資産税には、課税の基準となる「課税標準額」が一定の金額に満たない場合に、課税が免除される「免税点」という制度があります。
これは、価値が非常に低い固定資産にまで課税・徴収を行うと、役所が税金を計算したり通知書を送付したりする事務的な手間やコストのほうが、得られる税収よりも高くなってしまう可能性があるためです。このような非効率を避けるために、一定額以下の資産には課税しないというルールが設けられています。
免税点となる具体的な金額
免税点となる金額は、地方税法によって資産の種類ごとに以下のように定められています。
土 地:30万円未満
家 屋:20万円未満
償却資産:150万円未満
所有している資産の課税標準額が、それぞれ上記の金額に満たない場合は、その資産に対する固定資産税は課税されません。
最も重要な注意点:判定は「所有者ごと・市町村ごと」の合計額
免税点を考える上で最も重要なのは、この判定が一つの土地や建物ごとではなく、「同一の市区町村内に、同一の名義人が所有する資産の合計額」で判断されるという点です。
例えば、A市内に、あなたが所有する甲土地(課税標準額20万円)と乙土地(課税標準額15万円)があったとします。甲土地も乙土地もそれぞれ30万円未満ですが、A市内にあなたが所有する土地の課税標準額の合計は35万円となり、免税点の30万円を超えてしまいます。
この場合、免税点の対象とはならず、甲土地と乙土地の両方に対して固定資産税が課税されることになりますので注意が必要です。
固定資産税の計算方法

固定資産税は、固定資産税評価額と呼ばれる基準価額を基に算出され、土地の面積や地域、建物の構造や築年数などによって税額が変わります。
固定資産税は土地と建物に分けて計算されるため、それぞれの計算方法を見ていきましょう。
土地の固定資産税
土地の固定資産税は、以下の手順に沿って計算することになります。
- ●固定資産税評価額の調査
- ●課税標準額の計算
- ●課税標準額×税率の計算
ご自身が支払う固定資産税額を把握するためにも、一つずつ細かく確認していきましょう。
固定資産税評価額の調査
まずは固定資産税評価額の調査を行いましょう。
固定資産税を計算するうえで固定資産税評価額の調査は欠かせません。
固定資産税評価額の調査方法は3つあります。
売買価格から概算値を算出
土地の固定資産税評価額の概算値は「売買価格の70%程度」です。
例えば、2,000万円で売買が行われている土地の場合、固定資産税評価額は1,400万円程度となります。
土地の固定資産税評価額について、概算値を知りたい人は売買価格の70%程度と覚えておきましょう。
固定資産税路線価から概算値を算出
土地の固定資産税評価額は固定資産税路線価と面積によっても概算できます。
固定資産税路線価とは、道路ごとに1㎡あたりの評価額が定められており、全国地価マップから確認できます。
郊外などで固定資産税路線価が確認できない場合は、全国地価マップ上で赤い丸印がされている路線価を参考にしましょう。
固定資産税評価額は固定資産税路線価と土地の面積をかけることで算出できます。
例えば、1㎡あたり20万円の路線価の場所で200㎡の土地がある場合は、土地の固定資産税評価額は4,000万円ということになります。
ただし、土地の形状などによって軽減措置を適用できる場合もあるため注意しましょう。
正確な固定資産税評価額の確認方法
最後に、正確な固定資産税評価額の確認方法を紹介します。
正確な土地の固定資産税を確認するためには、毎年4月~6月頃を目安に郵送される納税通知書を確認しましょう。
納税通知書の課税明細書を確認することで、正確な固定資産税評価額を把握できます。
また、役所の市民税課などで「固定資産税評価証明書」を取得することで固定資産税評価額を確認することができます。
納税通知書を紛失してしまった場合には、市民税課などに問い合わせをしてみましょう。
ただし、市民税課などで固定資産税評価証明書を受け取れるのは所有者や同居の親族、相続人などに限られ、申請する際に必要な書類などもあるため事前に確認しておくべきです。
課税標準額の計算
次に、課税標準額の計算を行いましょう。
前述した固定資産税評価額をもとに軽減措置などを考慮したものが課税標準額ですが、課税標準額は市区町村によって軽減される内容が異なります。
具体的な軽減措置などについては後述しますが、住宅用地における200㎡まで土地の固定資産税が6分の1となる特例や、評価額が急激に上昇した場合にも税負担の上昇をゆるやかにする「負担調整措置」と呼ばれる制度もあります。
例えば、土地の面積が200㎡で固定資産税評価額が4,000万円の場合、課税標準額は4,000万円の6分の1で約660万円です。
負担調整率については計算方法が複雑になるため、各市区町村のホームページで確認してみましょう。
課税標準額×税率の計算
最後に、課税標準額×税率を計算しましょう。
市区町村によって税率が異なりますが、一般的に固定資産税は1.4%です。
例えば、先述した課税標準額が660万円の場合の固定資産税は660万円×1.4%で、年間92,400円となります。
建物の固定資産税
建物の固定資産税の具体的な計算方法を紹介します。
注文住宅を含めた建物の固定資産税も、土地の固定資産税と同様の手順で計算することになります。
固定資産税評価額の調査
新築の建物の固定資産税評価額は、建築費の60~70%程度で概算値を算出することができます。
例えば、建築費が2,000万円の注文住宅の場合は、固定資産税評価額は1,200~1,400万円ということになります。
また、正確な建物の固定資産税評価額を確認するためには、土地の固定資産税評価額と同様に、毎年4月~6月頃を目安に郵送される納税通知書の確認が必要です。
課税標準額の計算
土地と同様に、建物にも軽減措置が適用されることがあります。
長期優良住宅と呼ばれる良質な注文住宅を建てることで、新築住宅にかかる固定資産税が5年間2分の1となります。
6年目以降は、通常の固定資産税額に戻りますが「増税した」と考えないように注意しましょう。
課税標準額×税率の計算
建物の固定資産税の税率は、土地と同様に1.4%が一般的です。
そのため、これらの方法によって調査した固定資産税評価額に、1.4%をかけることで固定資産税を算出できます。
例えば、先述した固定資産税評価額が1,200万円の注文住宅の場合は、1,200万円×1.4%で年間168,000円となります。
注文住宅の固定資産税を安くする4つの方法

注文住宅の固定資産税を安くするためには、シンプルな家づくりを心掛けることが大切です。
- ●シンプルな間取りにする
- ●シンプルな屋根の形状にする
- ●コストがかかりにくい外壁材にする
- ●必要以上に豪華な設備にしない
注文住宅の固定資産税を安くする方法を把握しておくことで、ランニングコストを抑えることができます。
シンプルな間取りにする
1つ目の方法は、シンプルな間取りにすることです。
凹凸が多く複雑な形をした間取りの場合は、施工する面積が多くなるため固定資産税が高くなります。
そのため、固定資産税を安くするためには、部屋は四角形でシンプルな間取りにするのがおすすめです。
また、同じ広さでも小さな部屋が多数ある注文住宅と、大きな部屋が少数ある注文住宅では、後者の方が固定資産税が安くなります。
固定資産税を安くするためには、なるべく部屋の形をシンプルにして、部屋数を減らす必要がありますが、夢のマイホームを建てる際に税金のことばかり気にしたくない人もいるのではないでしょうか。
固定資産税を安くしながら、理想の注文住宅を建てるためには、専門家に相談するのがおすすめです。
シンプルな屋根の形状にする
2つ目の方法は、シンプルな形状の屋根にすることです。
屋根にはさまざまな材質や形状のものがあります。
具体的には、銅板やソーラーパネル、瓦などを使用している屋根や、勾配が大きい屋根は一般的に固定資産税が高くなります。
しかし、固定資産税が安い材質の屋根にすれば良いわけではなく、メンテナンス費用を考慮することも大切です。
例えば、年間の固定資産税が5万円安くなったとしても、10年間に一度の定期メンテナンス費用が50万円以上なるようであれば、材質の良い屋根材を選んだ方が賢明な判断と言えます。
そのため、固定資産税やメンテナンス費用のバランスを考慮しながら、専門家に相談するのがおすすめです。
コストがかかりにくい外壁材にする
3つ目の方法は、コストがかかりにくい外壁材にすることです。
注文住宅を建てる時は、外壁材や内装なども含めて自由に決められるのが醍醐味です。
しかし、高級な材質ばかり使用してしまうと、建築費が高くなり、結果的に固定資産税も高くなってしまいます。
また、窓や扉の数が多いほど、建てる際の工数が増えるため建築費が高くなります。
注文住宅の固定資産税を安くするためには、建築コストを抑えるために安い外壁材の使用が必要です。
ただし、屋根材と同じように良質な外壁材を使用することで、メンテナンス費用を抑えられることもあるため、長期的な視点でどちらが安くなるのかを検討するのが良いでしょう。
必要以上に豪華な設備にしない
4つ目の方法は、必要以上に豪華な設備にしないことです。
土地や建物の規模が大きくなれば固定資産税額も大きくなりますが、先述したように建物内外の間取りや設備、材質によっても変動します。
暮らしをより快適にする豪華な設備であればあるほど、固定資産税の基準となる標準評点数が高くなり、多額の固定資産税がかかるようになります。
固定資産税が多くかからないように、全ての設備を豪華にするのではなく、必要に応じてグレードの高い設備を導入するのがおすすめです。
注文住宅の建て方を工夫して固定資産税の軽減措置を適用する
注文住宅の固定資産税を安くする方法を4つ紹介しましたが、建て方を工夫して軽減措置を適用することで、大幅に固定資産税を軽減できる可能性があります。
固定資産税を軽減させるための特例や減額措置について以下の4つを紹介します。
- ●住宅用地の場合
- ●新築住宅の場合
- ●認定長期優良住宅の場合
- ●建て替えやリフォームをした場合
ご自身が所有している土地が適用条件を満たすかどうか、1つずつ確認していきましょう。
住宅用地の場合
まずは、住宅が建っている土地の場合です。
住宅が建っている土地の特例は、毎年1月1日時点において住宅やアパートなどの「人が住むための建物」が所在している場合に適用されます。
この特例は土地の面積によって軽減される割合が以下のように異なります。
- ●200㎡以下の土地:課税標準額の6分の1(都市計画税は3分の1)
- ●200㎡を超える土地:課税標準額の3分の1(都市計画税は3分の2)
例えば、固定資産税評価額が4,000万円の400㎡の土地に一戸建てが建てられている場合の固定資産税は、200㎡までが6分の1、残りの200㎡が3分の1となり、以下のような計算式で算出します。
- 1. 固定資産税(200㎡まで):4,000万円×200/400×1/6×1.4%=約46,600円
- 2. 固定資産税(上記以外):4,000万円×200/400×1/3×1.4%=約93,300円
- 3. 固定資産税合計:約46,600円+約93,300円=約139,900円
つまり、年間約14万円の固定資産税を支払うことになります。
新築住宅の場合
次に、新築住宅の場合です。
新築住宅の特例は、良質な住宅の建設を促すため、一戸建て住宅にかかる固定資産税を3年間2分の1に軽減する制度です。新築住宅の特例は全国共通で以下の要件を満たす必要があります。
- ●新築の時期が令和8年3月31日までであること
- ●床面積の半分以上が居住面積であること
- ●居住面積が50㎡以上280㎡以下であること(賃貸住宅の場合は40㎡以上280㎡以下)
ただし、土地の固定資産税や建物の都市計画税には適用されないため、上記の特例で2分の1となるのは建物の固定資産税である点にも注意が必要です。
認定長期優良住宅の場合
次に、認定長期優良住宅の場合です。
認定長期優良住宅の特例は、新築した住宅が認定長期優良住宅の場合に新築戸建ての特例が3年から5年に延長される制度です。
認定長期優良住宅とは、国が定めた要件を満たした新築住宅のことを指します。
具体的な要件としては、建物が地震に強く、安全な構造であることや高い断熱性能を持つことが求められます。
また、エネルギー効率の高い設備を備え、一定の省エネ基準を満たすことが必要です。
さらに、長期間にわたって住宅の機能や品質を維持するため、耐久性の高い建材や設備の使用が求められるケースもあります。
認定長期優良住宅の特例は新築住宅の特例と同様に、固定資産税が軽減されるのは土地ではなく建物である点には注意が必要です。
建て替えやリフォームをした場合
最後に、建て替えやリフォームをした場合です。
建て替えやリフォームにおける特例は、市区町村によって適用要件や減額の割合が異なります。
例えば神戸市の場合、建て替え、省エネ改修工事、バリアフリー改修工事をした場合に固定資産税の軽減措置が適用されます。
建て替えの場合
1月1日をまたいで建て替えをする場合に、以下の要件を満たすことで土地の固定資産税について住宅の特例を継続することができます。
- ●前年度の1月1日時点で住宅が建っている土地であること
- ●家を建てる前に居住以外の目的で使用していないこと
- ●当該年度の1月1日時点で基礎工事に着手していること
- ●翌年度の1月1日までに家が完成すること
- ●建て替えをする前後で同じ土地で家が建てられていること
- ●借地人が取得した場合を除き、前年度の1月1日時点における土地の所有者と当該年度の所有者が同じであること
- ●前年度の1月1日時点における建物の所有者と当該年度の所有者が同じであること
上記要件を満たす場合には、1月31日までに申告書や建築確認通知書の写しを持参して固定資産税課に申告しましょう。
省エネ改修工事の場合
省エネ改修工事をして建物の固定資産税について軽減措置を受けるためには、以下の住宅要件を満たす必要があります。
- ●規定の省エネ工事を令和8年3月31日までに行なっていること
- ●平成26年4月1日より前から居住用の建物であること
- ●改修工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- ●床面積の半分以上が居住面積であること
また、以下3つの工事について自己負担の金額が60万円を超える工事である必要があります。
- ●窓の断熱性を高めるための改修工事
- ●窓の断熱性を高める改修工事と同時に行う天井や壁、床の断熱性を高めるための改修工事
- ●外気等に接する窓や天井などの工事をすることで、省エネ基準を満たせる工事
上記の住宅に関する要件と工事内容に関する要件を満たすことで、改修工事が完了した翌年度分に限り床面積120㎡までの固定資産税の3分の1が減額されます。
バリアフリー改修工事の場合
バリアフリー改修工事をして建物の固定資産税について軽減措置を受けるためには、以下の住宅要件を満たす必要があります。
- ●新築から10年以上経過していること
- ●改修工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- ●床面積の半分以上が居住面積であること
また、居住者に関する要件は以下の通りです。 - ●65歳以上の人
- ●要介護認定または要支援認定を受けている人
- ●一定の障がいのある人(地方税法施行令第7条)
さらに、以下8つの工事について自己負担の金額が50万円を超える工事である必要があります。 - ●廊下幅を広げる工事
- ●階段の傾斜を緩やかにする工事
- ●浴室の改良
- ●便所の改良
- ●手すりの設置
- ●屋内段差の解消
- ●出入口の戸を改良する工事
- ●床表面の滑り止め化
上記の住宅、居住者、工事内容の3つに関する要件を満たすことで、改修工事が完了した翌年度分に限り床面積100㎡までの固定資産税の3分の1が減額されます。
注文住宅の固定資産税を節税するための4つのポイント

注文住宅の固定資産税を節税するためのポイントは、以下の4つです。
- ●新築住宅を建築する
- ●長期優良住宅の要件を満たす
- ●家屋調査では真摯に対応する
- ●クレジットカードで固定資産税の支払いをする
節税の方法を知っておくことで、無駄な税金を支払わずに済むため、1つずつ確認していきましょう。
新築住宅を建築する
1つ目のポイントは、新築住宅を建築することです。
先述したように、新築住宅を建てることで注文住宅にかかる固定資産税が3年間2分の1となります。
例えば、年間20万円の固定資産税が課税されていれば、年間10万円、3年で30万円の節税が可能です。
そのため、中古住宅を購入するよりも固定資産税を安くできる可能性があるでしょう。
ただし、面積などの要件を満たす必要があるため、注意が必要です。
長期優良住宅の要件を満たす
2つ目のポイントは、長期優良住宅の要件を満たすことです。
新築住宅を建てることで固定資産税が3年間2分の1となりますが、更に長期優良住宅の要件を満たすことで、5年間に延長されます。
先述した例だと、5年間で50万円節税できることになります。
長期優良住宅の要件を満たすためには、質の高い注文住宅にする必要があるため、建築コストが高くなる点には注意が必要です。
建築コストやランニングコストのバランスを考慮する必要があります。
家屋調査では真摯に対応する
3つ目のポイントは、家屋調査では真摯に対応することです。
固定資産税は、先述したように決められた計算式に則って計算されますが、家屋調査に来て評価をするのは「人間」です。
誤った評価によって固定資産税額が算出されてしまうと、必要以上に高い固定資産税を支払うことになる可能性があります。
そのため、質問などをされた際は真摯に対応し、冒頭に解説した計算方法で間違いがないか確認することも大切です。
自分で判断が難しい場合には、税金のプロである税理士に相談しましょう。
クレジットカードで固定資産税の支払いをする
4つ目のポイントは、クレジットカードで固定資産税の支払いをすることです。
クレジットカードで固定資産税を支払うことで、直接的ではないですが支払いの負担を軽減できるようになります。
年会費無料のクレジットカードは、ポイント還元率が1%であることが多いです。
例えば、年間20万円の固定資産税を支払っている場合、クレジットカードで支払うことで年間2,000円分のポイントを獲得できます。
注文住宅は長期で住むことが多いため、30年間カードで支払えば60,000円分のポイントを獲得できることになります。
厳密に言うと節税ではありませんが、賢く支払うのがおすすめです。
注文住宅の固定資産税に関する3つの重要注意点

注文住宅は、間取りやデザインだけでなく、税金の知識も重要です。特に固定資産税は毎年支払い続けるため、後から「知らなかった」と後悔しないよう、以下の3つの注意点をしっかり押さえておきましょう。
建て替え時の「更地期間」に注意!税金が最大6倍になるリスク
古い家を解体して新しい家を建てる場合、一時的に土地が「更地」になります。この期間が年をまたいでしまうと、固定資産税が急激に高くなるリスクがあるため、最大限の注意が必要です。
固定資産税は、毎年「1月1日時点」の土地の状況で課税額が決まります。土地の上に住宅が建っていると、「住宅用地の特例」が適用され、土地の課税標準額が最大で6分の1に軽減されます。しかし、1月1日に更地の状態だとこの特例が適用されず、土地の固定資産税が最大で6倍に跳ね上がってしまうのです。
最も確実な対策は、解体から新居の完成までを同じ年内に終え、年をまたいで更地の状態にしないことです。しかし、工期によっては難しい場合も多いでしょう。その場合は、前年のうちに新しい家の「建築確認」を取得しておくなど、1月1日時点で「建て替え中である」ことを証明できる状態にしておく必要があります。自治体によって特例継続の要件が異なる場合があるため、建て替え計画の段階で、必ず市区町村の役場(資産税課など)に相談・確認することが非常に重要です。
家屋調査では「聞かれたことだけ」に答えるのが賢明
新築後、市区町村の職員が訪問し、建物の構造や内外装、設備などを確認する「家屋調査」が行われます。これは固定資産税評価額を算出するための重要な調査ですが、ここでの対応次第で税額が変わる可能性があります。
固定資産税は、使われている資材や設備のグレードが高いほど評価額も上がります。こだわりの注文住宅だと、つい職員に自慢したくなるかもしれませんが、それは得策ではありません。例えば、「この壁紙はイタリア製の高級品で…」「このシステムキッチンは最高級グレードのものを入れました」など、聞かれてもいないのに自ら高級であることをアピールすると、標準的な資材・設備よりも高い評価額が付けられてしまう可能性があります。
もちろん、嘘をつくのは絶対に良くありません。虚偽の申告は後で問題になります。ポイントは、「聞かれたことに対して、事実をありのままに、淡々と答える」という姿勢です。家屋調査は自慢の我が家を披露する場ではなく、税額を決定するための事務的な手続きであると割り切って対応するのが賢明と言えるでしょう。
その設備、評価額上がります!対象となる設備を理解しよう
快適な暮らしのために導入する様々な設備も、固定資産税の評価対象になるものとならないものがあります。「家屋と一体化していて、取り外しが困難な設備」は、家屋の一部と見なされ評価額が上がるのが原則です。
評価額が上がる主な設備:
- ●全館空調、ビルトインエアコン
- ●床暖房
- ●ホームエレベーター
- ●ビルトイン食洗機
- ●屋根と一体化した「建材一体型」の太陽光パネル
※特に注意が必要な太陽光パネル:屋根の上に後から載せるだけの一般的な「屋根置き型」の太陽光パネルは、家屋の評価には含まれないことが多いです。しかし、一定以上の発電量があり売電収入を得る場合は、事業用の資産と見なされ、「償却資産」として別途固定資産税が課税されるケースがあるので注意が必要です。
これらの設備は生活の質を向上させるものですが、導入コストだけでなく、将来の固定資産税の増加分も考慮して資金計画を立てることが重要です。
注文住宅の固定資産税に関するよくある質問
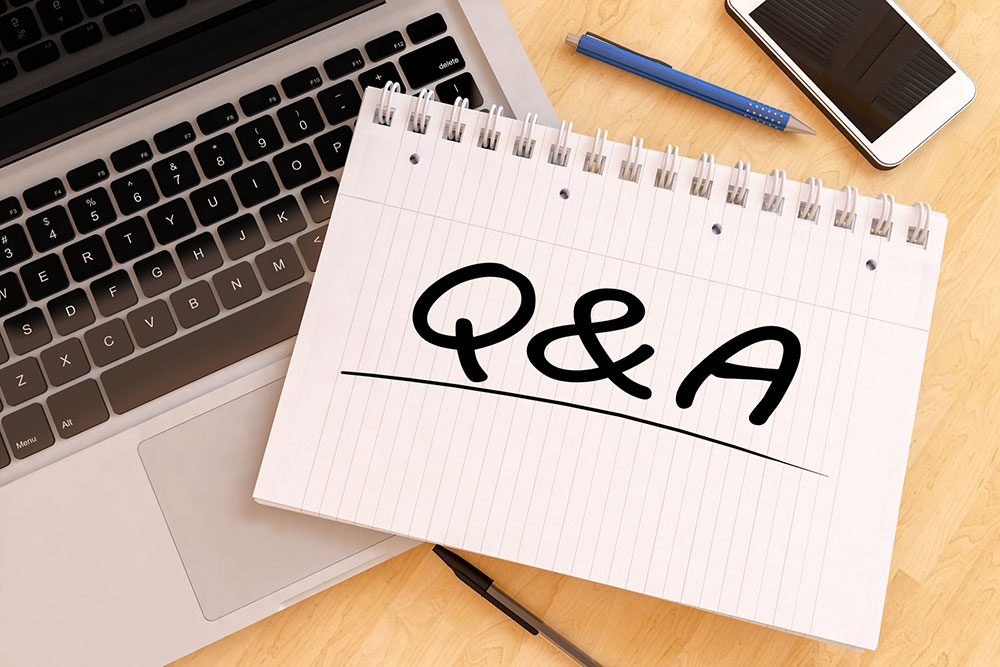
Q.家屋調査はいつ、どのように行われますか?
A. 家屋調査は、住宅が完成してからおおむね1〜3ヶ月後に行われるのが一般的です。
調査の前に、市区町村の役場(資産税課など)から所有者宛てに、日程調整のための通知書や電話連絡が来ます。調査当日は、役場の職員が2名ほどで訪問し、所有者立ち会いのもとで実施されます。
調査では、事前に提出されている建築確認申請の図面を基に、間取り、各部屋の内装材(壁、床、天井)、外壁や屋根の素材、キッチン・トイレ・お風呂といった設備のグレードなどを確認していきます。所要時間は建物の規模にもよりますが、通常30分〜1時間程度で終了します。この調査結果が、建物の固定資産税評価額を算出する基礎となります。
Q.二世帯住宅にすると固定資産税は安くなりますか?
A. 条件を満たせば、安くなる可能性が高いです。
ポイントは、その二世帯住宅が税法上「2戸の独立した住宅」とみなされるかどうかです。具体的には、玄関、キッチン、トイレ、浴室などが各世帯で完全に独立しており、壁やドアで仕切られている「構造上の独立性」が求められます。
この条件を満たし、さらに法務局で「区分登記」を行うことで、それぞれの世帯(住戸)が新築住宅の軽減措置(最大で3年間、税額が1/2)を個別に受けられるようになります。これにより、1戸の大きな住宅として建てた場合よりも、軽減される税額の総額が大きくなる可能性があります。
ただし、完全に分離した間取りにする必要があるため、建築コストが上がる側面もあります。税金のメリットと建築コストを総合的に判断することが重要です。
Q.太陽光パネルや全館空調を設置すると、税金はどれくらい上がりますか?
A.一概に「いくら上がる」と断言することはできません。評価額は、設備のグレード、設置面積(規模)、そして各自治体が定める評価基準によって大きく異なるためです。
一般的には、こうした豪華な設備は家屋と一体化した資産と見なされ、固定資産税の評価額に加算されます。目安としては、年間の固定資産税が数千円から数万円程度高くなる可能性があると考えておくとよいでしょう。
特に太陽光パネルは注意が必要で、屋根と一体化した「建材一体型」は家屋の評価額に含まれます。一方、屋根の上に載せるだけの一般的なタイプは家屋の評価には含まれませんが、発電出力が10kW以上で売電収入がある場合は、事業用の資産(償却資産)として別途課税対象になるケースがあります。
Q.平屋と2階建てでは、どちらが固定資産税は安いですか?
A. 同じ延床面積の場合、一般的に「2階建て」の方が固定資産税は安くなる傾向にあります。
理由は主に2つあります。
建物の評価額: 同じ延床面積でも、平屋は2階建てに比べて屋根と基礎の面積が単純に2倍近くなります。屋根や基礎は評価額を算出する上で重要な部分であり、その面積が広い平屋の方が、使用する資材が多いと見なされ、建物の評価額が高くなる傾向があります。
土地の評価額: 同じ広さの家を建てるなら、平屋の方がより広い土地を必要とします。当然、所有する土地の面積が広くなれば、その分土地にかかる固定資産税も高くなります。
これらの理由から、税金面だけを考えると、同じ延床面積であれば2階建ての方が有利と言えるでしょう。
まとめ|ポイントを抑えて固定資産税を安くしよう!
今回の記事では、注文住宅の固定資産税を安くする方法について紹介しました。
必要以上に豪華な設備や材質のものを導入すると、多額の固定資産税がかかることがあるため、必要に応じたグレードの設備や材質のものを導入しましょう。
固定資産税の軽減措置や特例制度を活用することで大幅に軽減できる可能性があります。固定資産税を安くするために、正しい知識を身に付けておきましょう!


効果的に節税しながら理想の家を建てるには、まずは具体的な住まいを実際に見て
理想のイメージを具体化することが大切です。
お近くのABCハウジングで気になるハウスメーカーを見学して、理想のイメージをふくらませてみませんか。




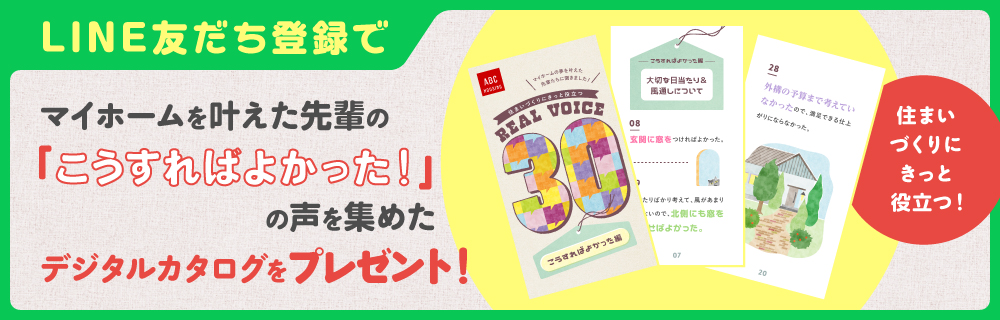
 前の記事
前の記事