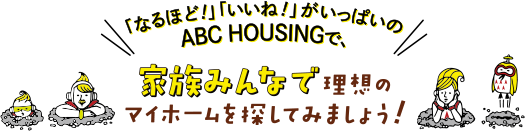住まいの間取りや広さを検討しようと考えはじめても、なかなか実際のイメージと結びつけるのは難しいものです。また長い間、住みつづけていく中では、家族構成や子どもの成長など住まい方の変化がつきものです。図面を見ただけでは「この広さで本当に快適に暮らせるだろうか」「将来の変化に対応できる間取りなのか」と疑問に思われるかもしれません。
家族に合わせた機能的な間取りになっているか、ちょうどよい広さが確保できているかは、家族のプライバシーの確保や家族団らんに大きく影響します。住み心地や生活の質を左右する最も重要なポイントの一つと言えるでしょう。
そこで今回は、一戸建てに住む4人家族を想定して、ご家族で話し合う際に役立つ適切な広さや間取りの考え方について紹介します。
4人家族の一戸建ての広さを統計値から考える

はじめに、4人家族が暮らす一戸建ての広さについて統計数字から確認していきましょう。
4人家族に必要な広さは?
令和3年3月に閣議決定された国土交通省の「住生活基本計画(全国計画)」の中で、4人家族が健康で文化的な住生活を営む上で必要最低限な住宅の面積として「最低居住面積水準」が示されています。
最低居住面積水準=10㎡×世帯人数(4人)+10㎡=50㎡
しかし、この広さは最低限生活できる広さであり、4人家族が子育てしながら快適に暮らすには手狭すぎる面積と言えます。どんなサイズの間取りになるかの目安など、詳しい内容については次の章で解説します。
4人家族がゆとりをもって暮らせる広さは?
4人家族がゆとりを持って豊かな住生活を送るには、より広い面積が求められます。
国土交通省の「住生活基本計画」において、豊かな住生活の実現と多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積として、「誘導居住面積水準」が示されています。
一般型誘導居住面積水準=25㎡×世帯人数(4人)+25㎡=125㎡
※郊外や都心部以外の戸建て住宅を想定
都市居住型誘導居住面積水準=20㎡×世帯人数(4人)+15㎡=95㎡
※都心とその周辺での共同住宅を想定
95㎡を下回ると、空間のゆとりが取りづらく、子ども部屋のプライバシーが十分に確保できなかったり、リビングが窮屈に感じたりする可能性があります。
4人家族が暮らす住まいの平均的な広さは?
実際に、4人家族が住んでいる戸建て住宅の平均的な広さはどれくらいなのでしょうか。
住宅金融支援機構が実施した2022年度の「フラット35」利用者調査によると注文住宅融資を利用した世帯の平均家族人数は3.6人、平均住宅面積は122.8㎡でした。
フラット35利用者を対象とした調査ではありますが、フラット35は多くの世帯で広く使われる公的ローンであり、全国の住宅の実態を反映したデータと言えます。
また、調査結果の平均家族人数は4人を下回る3.6人でしたが、一般的に家族人数が多いほど広い住宅に住む傾向があります。そのため、4人家族が暮らす平均的な広さとしては、120㎥を超える面積が目安値となると考えられます。
床面積ごとの広さのイメージ
4人家族が暮らすための目安面積について統計値から解説しましたが、間取りに当てはめて考えてみましょう。建物の広さごとにイメージできる間取りについて解説します。
50㎡(約15坪)

国土交通省の示す最低居住面積水準である50㎡の間取り例は以下の通りです。
- ・LDK 10畳程度
- ・主寝室 6畳(収納スペースを含む)
- ・子ども部屋 4.5畳×2室または9畳1室(収納スペースを含む)
- ・玄関・廊下 できるだけコンパクトな最低限の広さ
- ・収納スペース ほとんど確保することが難しい
このように、LDKはワンルームマンションでよく見かける10畳程度であり、家族がそろってくつろぐスペースを十分に確保するのは難しそうです。そのため、座卓やダイニングソファを利用して、リビングとダイニングの機能をまとめるなど暮らし方に工夫が必要です。
各部屋に収納を設けると、実質的に使えるスペースは主寝室5畳、子ども部屋4畳程度となります。また玄関やホール、水回りスペースも非常にコンパクトです。一般的な4人家族向けの住宅としてはギリギリの広さです。しかし、限られた空間を上手に活用し、動線や家具レイアウトなど工夫すれば、快適な暮らしを実現することもできます。
95㎡(約29坪)

国土交通省の示す都市居住型誘導居住面積水準である95㎡の間取り例は以下の通りです。
- ・LDK 14畳程度
- ・主寝室 8畳+ウォークインクローゼット
- ・子ども部屋 5畳×2室(収納スペースを含む)
- ・その他の収納スペースも確保可能
この広さであれば、4人家族でストレスを感じずに暮らせる間取りづくりが実現できそうです。各部屋やホールにも必要な収納が確保できます。ただし、和室や客間などを設置する余裕はないため、将来的な変化に十分に対応することは難しい可能性があります。
120㎡前後(約36坪)

国土交通省の示す一般型誘導居住面積水準やフラット35利用者調査の平均値である120㎡前後の間取り例は以下の通りです。
- ・LDK 20畳程度
- ・主寝室 10畳+ウォークインクローゼット
- ・子ども部屋 6畳×2室(収納スペースを含む)
- ・その他スペース(畳コーナー、ファミリークローゼット、書斎など)
この間取りであれば、4人家族でゆとりを持った生活をする様子が容易に想像できるのではないでしょうか。その他スペースは、将来的に他の用途へも変更可能ですが、そういったスペースが必要なければ、LDKの広さをさらに充実させることもできます。テレワークが多い場合でも適切なスペースを確保でき、不都合なく仕事に集中できそうです。
132㎡(約40坪)

図面では坪数で表示されることが多いので、次に約40坪の間取り例について解説します。
- ・LDK 25畳程度
- ・主寝室 10畳+ウォークインクローゼット
- ・子ども部屋 7畳×2室(収納スペースを含む)
- ・その他スペース(和室、客間など一部屋)
この広さがあれば、4人家族で十分なゆとりを持って暮らせるほか、水回りや収納にこだわることも可能です。将来的な変化にも対応しやすく、間取りの自由度も格段にアップします。
165㎡(約50坪)

約50坪の間取り例について解説します。
- ・LDK 25畳程度
- ・主寝室 10畳+ウォークインクローゼット
- ・子ども部屋 8畳×2室(収納スペースを含む)
- ・ファミリークローゼットまたはホームシアターなどの趣味の空間
- ・その他スペース(和室、客間など一部屋)
- ・余裕のある玄関ホールや階段周り
50坪の広さになれば、家の中でどのスペースを充実させたいか、家族のこだわりを存分に取り入れられます。LDKを30畳以上にして一層ゆとりを持たせたい、水回りを充実させて家事効率をアップさせたい、趣味の空間やホームオフィスを作りたいなど、理想の間取りを実現しやすくなります。
4人家族が暮らす一戸建ての間取りを考えるポイント
我が家にぴったりの間取りをつくるために考えるべき点について解説します。
必要な部屋数から考える

まず、どこの家庭でも必要となる基本的な間取りはLDK、主寝室、子ども部屋、水回りスペースです。
子ども部屋の設置については、性別や年齢差によって様々な考え方がありますが、子どもの成長に合わせて、それぞれ個室を確保する必要があります。また、遠方に住む両親や友人が遊びに来た際に宿泊できるスペースとして、客間を設けることも選択肢の一つです。
来客との関係性や頻度によっては、用途を限定しない多目的ルームを設けるのも一案です。来客時は客間として、普段は趣味の部屋やホームオフィスとして使うなど、フレキシブルな使い方ができると使い勝手が向上します。
部屋数を多く確保しておけば、将来の変化にも対応しやすくなる一方、部屋数を増やした分、それぞれの部屋や空間に十分なゆとりを持たせられなくなる可能性があります。客間を設ける場合は、来客時の布団収納スペースも合わせて確保する必要があります。布団の収納には、ある程度のスペースが必要なのであらかじめ考慮しましょう。
このように、普段家族が利用する空間にゆとりを持たせることと、特別なタイミングで必要となるスペースを準備することのどちらを優先したいかをよく考える必要があります。必要最低限の部屋以外については、バランスの取れた間取り計画が理想的といえるでしょう。
ライフプランから考える
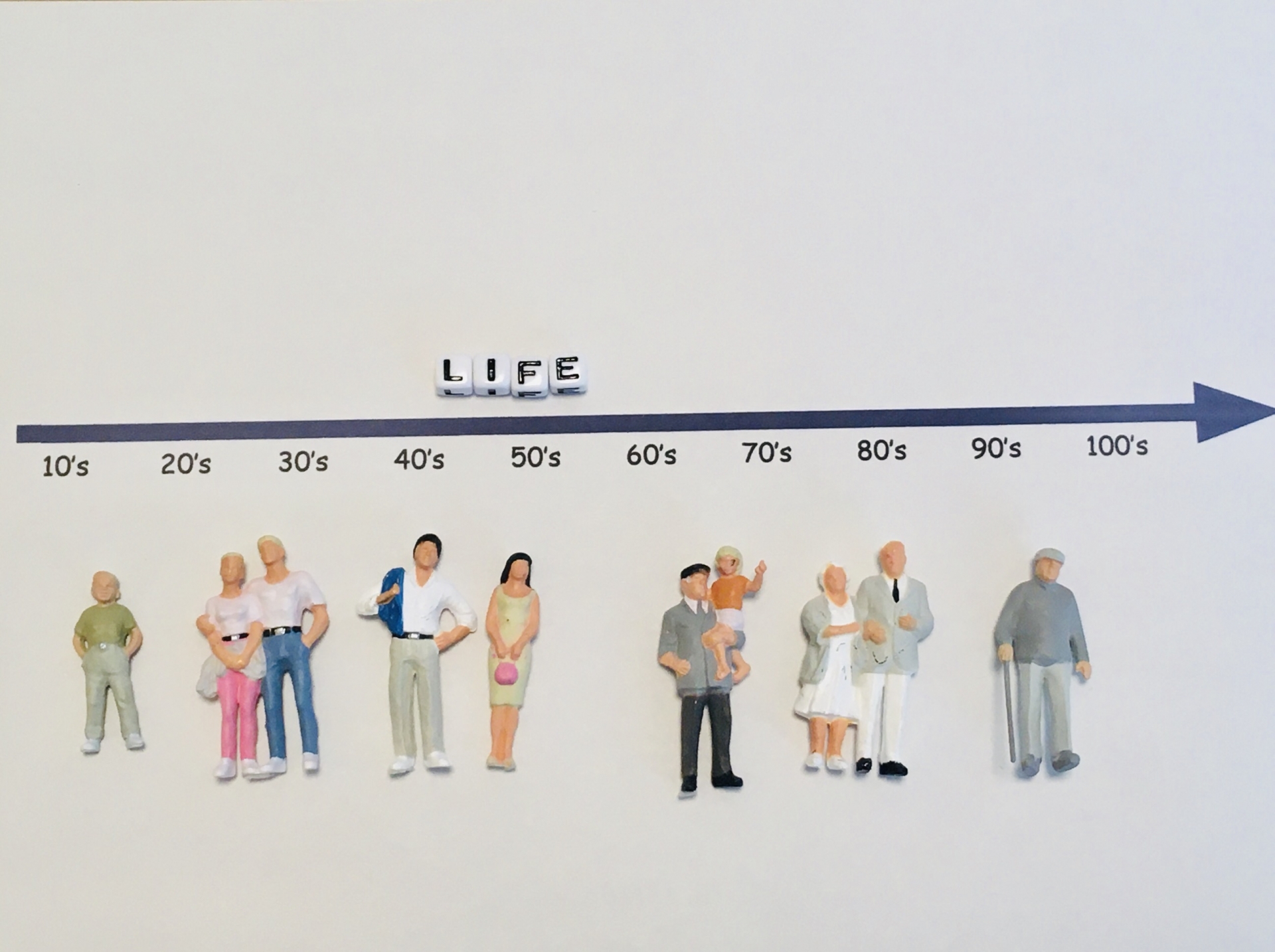
家族構成の変化や子どもの成長によって、使い方が大きく変わるスペースについて、将来的な使い方を考えてみましょう。
子ども部屋が必要なのは?

夫婦+子ども2人の4人家族の場合、子どもが乳幼児期から小学生低学年の頃は、男女を問わず子ども部屋は1室でも問題ないケースが大半です。しかし、タイミングに差はありますが、兄弟の性別や性格によって概ね小学生高学年~思春期までには子ども部屋を2室に分ける必要があります。
ここで、兄弟の年齢差を考慮して子ども部屋2室が必要な期間を考えてみましょう。例えば、3歳差兄弟の場合、上の子が10歳の時点で個室を与え、下の子が22歳の時点で独立すると仮定した場合、子ども部屋が必要な期間はおよそ15年間と計算できます。子どもが独立し、夫婦二人になれば子ども部屋は不要となるので、趣味の部屋、ホームオフィスなどに転用することも可能です。
将来的に親世帯の同居を考える場合は、使わなくなった子ども部屋を転用する方法もあるので、それを見据えてあらかじめ子ども部屋を1階に配置するのも一案です。
水回りや玄関周りの動線

子育て時期は、効率的な家事動線が特に重要視されることが大半です。また、老後期には、玄関やトイレ、浴室などに車椅子でもアクセスしやすい動線や、手すりを設置できる余裕が求められます。
間取りを作成する際に、将来的にリフォームが必要となった場合を想定し、リフォームしやすい間取りを計画しておくのも一案です。
家族のライフスタイルから考える

「テレワークの頻度が高い」「家族に介護が必要な人がいる」など、家族のライフスタイルや特別な事情がある場合、間取りづくりにおける優先順位が異なります。様々な家族の状況を想定して、柔軟に対応できる「幅を持った間取り」を考えましょう。
①テレワーク時の作業場所

仕事内容にもよりますが、静かな個室が必要なケースもあります。それは、オンライン会議や機密情報の取り扱いに対応できる空間が必要な場合などです。
1か月に数回程度であれば、その時だけリビングで作業することもできます。しかし、テレワークと通勤が半々の場合など、自宅で仕事をする頻度が高い場合は、書斎や予備室をワークスペースとして確保することには大きなメリットがあります。
リビングなど家族共有の空間で仕事をする場合、家族は仕事に集中できる環境をつくろうと、できるだけ静かに過ごしたり、オンライン画面への映り込みに配慮したいと考え、お互いにストレスや生活のしにくさが起きるものです。専用スペースを確保できれば、落ち着いて仕事に打ち込めるだけでなく、家族への影響も最小限に抑えられます。
②バリアフリー対応

家族に介護が必要な方や障がいを持った方がいる場合は、玄関や廊下の移動のしやすさや、浴室やトイレなどの使いやすさが何よりも優先されます。また、手すりの設置や段差のない床など家庭内での事故防止への配慮も欠かせません。
さらに、将来的な車いす生活や親世帯との同居を視野に入れる場合は、その状況に備えた間取りを検討しましょう。車いすでの動線を想定して建具や廊下の幅にゆとりを持たせたり、ゆったりとしたスペースを確保したりして介護する家族が動きやすい作りにするなど、誰もが無理せず快適に暮らすための配慮が重要です。
自宅での理想の過ごし方を大切にして広さを考える

家族一人ひとりの理想の暮らしや、みんなで過ごす時間をどのように過ごしたいかによっても間取りの優先順位は大きく異なります。先ほど解説した建物の大きさごとの部屋のサイズを参考にしつつ『我が家にとってぴったりのサイズ』の間取りを考えていきましょう。
LDK

週末、リビングで家族団らんを楽しめるようなゆったりサイズのソファを置きたい場合、広さの確保だけでなく、希望のソファサイズに合わせてLDKの形状を考えます。
また、みんなを呼んでホームパーティーを開きたい場合は、大人数が集まれるようにゆとりのある広さやリビングダイニングが一体となった間取りがおすすめです。オープンキッチンにすれば、普段は家族で一緒に料理を楽しめるだけでなく、来客時にもみんなで料理の準備から楽しむこともできます。
主寝室・子ども部屋

できるだけリビングで家族みんなが過ごすスタイルを重視する場合、あえて個室を充実させずに狭く設定することもできます。一方、子どもがある程度成長している場合は、プライベートな時間も重要なため、快適に過ごせる広さの確保が必要です。
他のスペースを優先し、個室の広さが取れない場合、作り付けの収納やクローゼットなどを用いて収納スペースを確保した方が、個室自体の面積は減りますが使い勝手がよくすっきりと過ごせます。
洗面所・浴室

一戸建てに住むなら、広々としたお風呂でゆっくりリラックスしたいと希望される方や、洗濯動線を効率化して最小限の動きですませたいと考える方も多いでしょう。
さらに、洗面化粧室では収納スペースの計画も大切です。洗面化粧室には、タオル、洗剤の在庫、清掃用具など、サイズも種類もばらばらのものを収納しますが、あらかじめ計画しておけば、すっきりした空間が保てます。
洗面所や浴室は、賃貸住宅や集合住宅ではコンパクトにまとめられることが多いですが、一から間取りを設計できる注文住宅ではこだわりの空間が叶えられます。
その他のスペース

開放的で圧迫感のない間取りにしたい場合、階段やホール、廊下にゆとりを持たせると、広々した雰囲気になります。階段や廊下の幅を90cm~120㎝程度確保できれば、かなり雰囲気が変わります。
また、趣味に没頭できる時間を大切にしたいなら専用のスペースを確保する、大型犬を飼うのが夢であれば犬と快適に暮らすための設備や間取りを重視するなど、家族の希望に合わせた間取りづくりは、より満足な住まいの実現において重要なポイントです。
間取りだけでなく、理想の生活を叶える動線にも注目しましょう。例えば、天気のよい週末には、庭でバーベキューを楽しみたい場合には、キッチンから庭まで食材を運ぶ動線や、リビングから庭へスムーズに行き来できる動線や出入り口を確保すれば、より快適に楽しめることでしょう。月に何度もバーベキューをしたいとイメージしているのであれば、その動線をメインとした間取りを検討するのも一案です。
間取りごとの特徴

部屋数ごとに向いている家族構成や、間取りの特徴について確認してみましょう。
2LDK

2LDKは、子育ての始まりの頃に適した間取りです。LDK+主寝室+子ども部屋(将来的に間仕切りする予定のワンルーム)といった構成が想定されます。
この間取りのメリットは、家事動線が確保しやすい点や、子どもが小さいうちはスペースを広く使える点です。子育て世帯にとって使い勝手が良い間取りであると言えるでしょう。
ただし、2LDKを選択する場合、建物自体がコンパクトであることも多いため、将来的に子ども部屋を間仕切りすると手狭になる可能性があります。また、部屋の数が少ない分、将来の子ども部屋として確保した部屋があいまいなスペースとなりがちで、雑多なもの置き場となってしまうリスクもあります。
3LDK

3LDKは、4人家族向けとして主流の間取りです。LDK+主寝室+子ども部屋×2、または、LDK+主寝室+子ども部屋(将来的に間仕切りする予定のワンルーム)+和室や客間などの間取りが考えられます。
この間取りのメリットは、部屋数に余裕があるので、ワーキングスペースや趣味の空間を作る、おもちゃ部屋を作るなど、用途に合わせて有効活用できる点です。また部屋以外の収納、ホール、階段などに余裕を持たせることもできます。
しかし、部屋以外のスペースに余裕を作った場合、子どもの成長とともに、子ども部屋が手狭になるリスクもあります。また、将来家族人数が増えた場合には、対応しきれず大幅なリフォームが必要となることもあるでしょう。
4LDK

4LDKはLDK+主寝室+子ども部屋×2+和室や客間といったゆとりのある間取りです。
将来的な家族人数の増加などの変化への対応に、特に重視した間取りと言えます。
子どもが異性の場合や年齢差がある場合など、近いうちに子ども部屋を2室確保する場合はあらかじめ2つに分割しておく方が好ましいでしょう。また、多目的に使える部屋がとれるので、家族の成長に合わせて、子どもの遊び場や書斎、親が同居する際の居室など目的に応じた使い方が自由にできます。この広さであれば、両親ともに同居して6人家族となった場合を仮定しても、比較的ゆとりを持って暮らすことができるのではないでしょうか。
ただし、部屋の数を増やすと、LDKのサイズや個室に割り振るスペースは狭くなります。また、個室の数が増えると、掃除の動線が長くなる可能性もあります。
それぞれの部屋に置かれた家具や収納部分など、掃除がしづらい箇所が増えるほか、掃除時の各部屋の行き来が多くなることがその要因です。
平屋

4人家族で平屋住宅を選ぶ場合、間取りと使い勝手についてメリット・デメリットを十分に検討する必要があります。
まずメリットとしては、高齢者や体が不自由な方でも階段を使わずフラットに移動できる点が挙げられます。また、敷地面積に余裕がある場合は間取りの自由度が高く、開放的なワンルームのような間取りも可能です。
平屋ならではのデメリットもあります。水平方向に広がる間取りとなるため、家事動線が長くなりがちなので、特に水回りの配置に配慮が必要です。
さらに、開放的な間取りは室内の音が伝わりやすく、プライバシーが確保しづらい課題もあります。4人家族が快適に暮らすには、プライベート空間とリビングなどの共有空間を上手に区切る工夫が欠かせません。逆に多くの部屋に区切る場合は、採光や通風をどのように保つかが課題となります。
このように平屋の場合、2階建て以上とは全く異なるメリット、デメリットがあるため、4人家族で平屋を検討する場合は、ご家族の使い勝手に合わせた間取りづくりが重要です。
月々の支出から逆算して間取りや広さを考える

住まいづくりを検討する際、住宅ローンの支払いだけでなく、光熱費を合計した月々の支出がどのように変化するのかを想定する必要があります。無理のない支出計画を立てるためにも、おさえておくべきポイントについて紹介します。
4人家族が暮らす一戸建ての光熱費の目安
120㎡程度の戸建ての場合、月々の目安として電気代5,000円~10,000円前後、ガス代8,000円~10,000円前後と言われています。建築地域や気候によって変動しますが、電気代とガス代の合計で20,000円程度を予定することがおすすめです。ただし、地域や気候によっても変動があり、寒冷地では冬季間の暖房費が20,000円以上になることもあります。
引っ越し前よりも光熱費がアップする要因
東京都環境局のWEBページには平成26年度の統計結果として、戸建て住宅に住む4人世帯と集合住宅に住む4人世帯の電気とガスの平均使用量が掲載されています。ガスの使用量は集合住宅316kWh、戸建住宅436kWh、電気の使用量は集合住宅46㎥、戸建住宅57㎥とあり、それぞれ約1.2~1.3倍の差があると計算できます。少し古いデータではありますが、近年でもその傾向に大きな変化はないと考えられるでしょう。
光熱費が高くなる主な要因としては、建物の面積が増えた分、冷暖房にかかる電気代が増えるほか、電気のアンペア数変更による基本料金アップも考えられます。また、浴槽のサイズアップは電気代、水道代の増加に直結します。
引っ越し前よりも光熱費がダウンする要因
築年数の経った一戸建てから新築住宅に引っ越した場合、光熱費が下がることも珍しくありません。新築住宅では断熱性が高く、高効率な設備が装備されており、暖房や給湯に必要なエネルギー消費量が削減できるため、光熱費を節約できる可能性が高いです。
まとめ

4人家族で一戸建て住宅の間取りや広さを検討する上で、大切な点を解説しました。家族のライフスタイルや将来的な変化を想定しながら、ゆとりある快適な住まいづくりを実現するためには重要なポイントについてまとめてお伝えします。
・家族がストレスなく生活できるライフスタイルに合わせた部屋数や空間の確保
・みんなで過ごすスペースとプライバシー確保のバランスをとること
・ご家族のニーズを反映させた『間取りの優先順位』を決めること
・子どもの成長や家族構成の変化を見据えて柔軟に対応できること
・光熱費の変化をふまえた支出面も検討して、無理のない計画であるか確認すること
『終の棲家』となる住まいづくりは人生における大きな選択の一つといえます。4人家族で快適に暮らしていくために、ご家族みんなの理想を実現した住まいづくりができれば、家族の笑顔あふれる毎日や高い満足感を得られるはずです。お住まいづくりを進める際にお役立ていただければと思います。




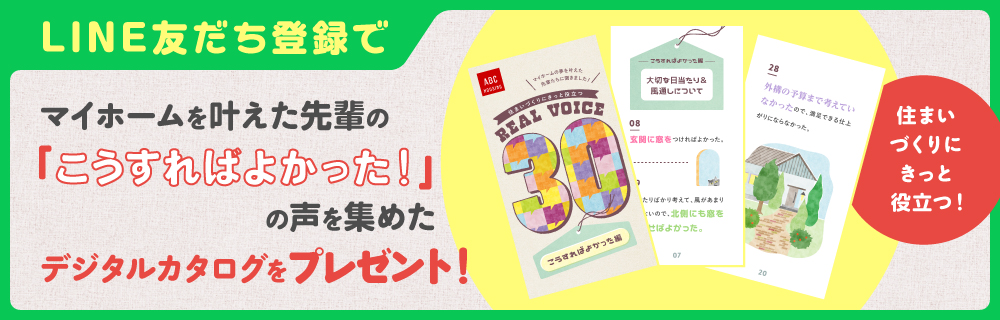
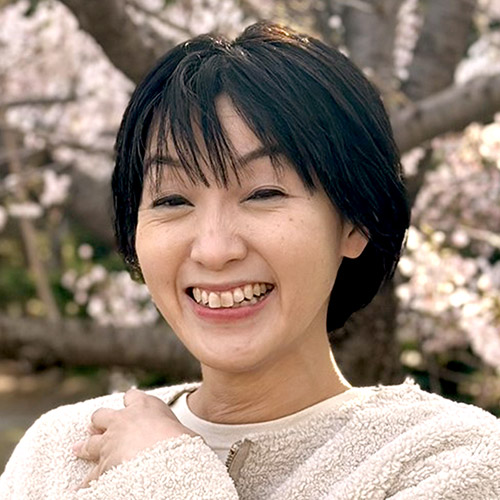
 前の記事
前の記事