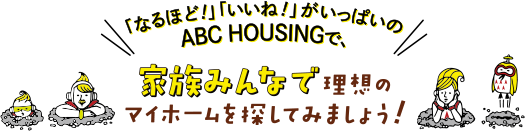近年では台風やゲリラ豪雨による水害が増加しており、注文住宅を建てる際にも水害に強い家づくりが求められるようになりました。都市部でも浸水被害が起こるケースもあるため、住宅の水害対策に不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、注文住宅に有効な水害対策として、土地探しに重要な水害の起こりやすい場所や、水害に強い家にするためのポイント、水害が起きた場合の対処法、補償制度などを紹介しています。注文住宅での家づくりを考えている方は、ぜひ参考にしてください。
水害が起こりやすい場所

水害対策を考えるためには、水害の起こりやすい場所を知っておくことが大切です。一般的に、水害が起こりやすいとされる土地や場所は、以下のとおりです。
- ●川・海に近い土地
- ●埋め立て地
- ●低地
- ●降水量の多い地域
それぞれの特徴を詳しく解説します。
川・海に近い土地
1つ目は、河川や海から近い土地です。大雨や台風による河川の氾濫や高潮、波浪などの影響を受けやすいため、住宅が浸水など水害に遭うリスクも高まります。海や川に近い土地は、風通しや景色が良い場合が多い反面、地盤が弱い傾向にある点にも注意が必要です。
埋め立て地
2つ目は埋め立て地です。湖や田んぼだった場所を人工的に埋め立ててできた土地は、地盤が弱く、水害にも遭いやすい傾向にあります。埋め立て地の水害リスクは現在の状態を見ただけでは判別できない場合も多く、以前はどのような土地であったかを調べるなどして、想定される自然災害の把握が必要です。国土交通省国土地理院の明治期の低湿地データにて確認ができます。
低地
3つ目は、周囲と比べて低い土地です。海抜や標高が低い土地では、大雨などの際に周囲から水が流れ込みやすくなります。特に、周囲を高台に囲まれた谷地などは注意が必要です。土地の標高やハザードマップを参考にして、事前に水害リスクを調べておきましょう。
降水量の多い地域
4つ目は、降水量が多い地域です。大雨が頻繁に発生する気象条件の地域では、そうではない土地と比べて水害が起こりやすくなります。同じ県内でも地域ごとに気候の特徴が異なる場合があるため、事前に過去の年間降水量などを確認しましょう。
水害に強い家にするためのポイント

ここからは、注文住宅を水害に強い家にするためのポイントを、以下の3段階に分けて解説します。
- ●土地探し
- ●建築時
- ●メンテナンス
それぞれのポイントを詳しくみていきましょう。
土地探し
以下では水害に強い注文住宅を建てるために、土地探しを行ううえで重要なポイントを解説します。
ハザードマップを確認する
水害を含めた自然災害の被害をできる限り防ぐには、極力リスクの低い土地を選ぶことが重要です。事前に各自治体のハザードマップで確認し、自然災害が予想される地域を把握しておきましょう。リスクの高い土地を避けられたり、リスクのある土地でも有効な対策を取りやすくなったりします。
建築時
以下では実際に注文住宅を建築する際、リスクを減らして水害に強い家をつくるためのポイントを解説します。
かさ上げ(盛土)する
かさ上げ(盛土)とは、住宅を建てる土地にあらかじめ土を盛って地盤を高くしておく工事方法です。かさ上げ(盛土)を行えば、土地全体が高くなるため水害に遭いにくくなります。ただし、かさ上げ(盛土)を実施する際は、土砂崩れが発生する危険性などがあるため配慮が必要です。
高床式にする
高床式は、住宅の基礎部分を高くする方法です。高床式にすると、大雨や台風の際に建物の床上への浸水を防ぎやすくなります。ただし、基礎部分の高い住宅は、道路斜線制限や隣地斜線制限など規制に抵触する場合もあるため、法令制限を遵守するとともに、近隣にも配慮して建築することが大切です。
高い塀・壁で囲む
高い塀や壁で土地を囲むと、水害時にも敷地内の浸水リスクを防ぎやすくなります。ただし、適切に排水が行われないと、かえってリスクが高まる恐れがあるため、塀・壁を設ける場合は敷地内の排水計画が重要です。また、住宅の日当たりに影響する可能性がある点にも注意しましょう。
防水性の高い外壁を採用する
防水性の高い外壁を採用する方法も、水害対策として有効です。1階部分の外周に鉄筋コンクリート造の腰壁(腰の高さより低い壁)を設けると、水害リスク低下に効果を発揮します。防水性の高い外壁は建築コストがかかりやすくなるため、全体ではなく一部のみ腰壁を採用するなど工夫すると良いでしょう。
2階以上を主要な生活空間とする
主要な生活空間を2階以上にすると、万が一家が浸水した場合でも、スムーズな避難が可能です。キッチンやリビング、トイレなどを2階に配置して、1階を使用できなくなったとしても問題なく暮らせる間取りにしておくと、生活を維持しやすくなります。
分電盤を1階と2階で分ける
分電盤を1階と2階で別々に設置するのも水害対策として有効です。浸水などで電気が使えなくなると、日常生活を送るのが困難になります。1階が浸水して使えなくなった場合でも、いつも通りに電気を使用した日常生活を送れるよう、2階にも分電盤を分けて設置しておくと良いでしょう。
メンテナンス
以下では、注文住宅を建てた後でメンテナンスを行う際に、水害に強い家を維持しておくためのポイントを解説します。
屋根・外壁を定期的に点検、塗り直しを行う
屋根や外壁に塗料の剥がれやひび割れなど破損がある場合は、大雨や台風の際に浸水リスクが高まります。住宅を建ててからも定期的に点検したり、塗料の塗り直しを行ったりすれば、不具合があった場合でも早期発見につながり、問題が大きくなる前に修復が可能です。
排水設備・雨樋の定期点検、清掃を行う
浸水リスクを防ぐには、適切な排水設備の設置や管理が重要です。設備があっても清掃を怠ると、落ち葉やゴミが溜まって詰まってしまい、排水の機能がなくなる可能性があります。普段からこまめな点検や清掃を行い、詰まりの原因になる落ち葉・ゴミなどを取り除いておくことが大切です。
万が一注文住宅で水害が起きた場合の対処法

ここからは、万が一居住中の注文住宅で水害が起きてしまった場合の対処法を、床下浸水と床上浸水のケースに分けて紹介します。
床下浸水
床下浸水とは、水害で床の上までは水が来ていなくても、住宅の基礎部分まで浸水してしまった状態です。床下浸水を放置すると、基礎部分にカビや劣化が発生したり、床下の電気配線から火災が起きたりするほか、流れ込んだ汚水や土砂から感染症になる危険性もあります。
床下浸水した場合の対処法として、床下に溜まった水や土砂を撤去し、きちんと乾燥させなければなりません。床下浸水は、火災保険の水害保証で対象外となる可能性もあるため、注意が必要です。
床上浸水
床上浸水は住宅の基礎部分だけでなく、床の上まで水が侵入してくる状態です。床上浸水が起きると、注文住宅の建材や断熱材まで水を吸ってしまい、内部でカビや劣化が起こるため、復旧にも大きな時間とコストを要します。
床上浸水した場合の対処法として、まずは汚れた部分を水で洗い流したり雑巾で水拭きしたり、消毒薬で消毒したりしなければなりません。また、床下の基礎部分には汚水や土砂が残っている場合があるため、同様に排水や処理が必要です。
注文住宅の水害発生時に活用できる補償制度

注文住宅で水害が発生した際には、さまざまな制度を利用して補償を受けられる場合があります。公的な支援制度と個人で加入する火災保険に分けて、補償内容をみていきましょう。
公的支援制度
住んでいる住宅が水害に遭った場合、国や自治体の支援制度から補償を受けられる場合があります。国が実施する被災者生活再建支援制度の支援金は、以下のとおりです。
- ●住宅が全壊した場合:100万円(基礎支援金)
- ●住宅の大規模半壊:50万円(基礎支援金)
- ●住宅の再建(建築・購入):200万円(加算支援金)
- ●住宅の補修:100万円(加算支援金)
- ●賃貸への引越し:50万円(加算支援金)
ほかにも、住宅の応急修理への支援や住宅を復旧する際の融資制度などもあり、各自治体でも浸水被害を防ぐ止水板の設置助成制度などを設けています。
火災保険の水災補償
個人で加入する火災保険にも、水災補償として、水害に遭った場合の補償内容が含まれている場合があります。建物だけでなく家財も対象になっており、保険会社によって細かな違いはあるものの、一般的には以下のような被害が保険金の支払い条件です。
- ●建物・家財の再調達価額(復旧にかかる費用)の30%以上の損害
- ●床上浸水の発生
- ●地盤から45cmを越える浸水の被害
一定の条件を満たす場合、保険金額の1.1倍や2倍などを限度とし、損害額から自己負担額を差し引いた金額が保険金として支払われます。台風や河川の氾濫、高潮、ゲリラ豪雨などによる被害が水災補償の対象となりますが、地震による津波の被害は対象外です。
住宅の水害から身を守るための備え

注文住宅の水害から身を守るためには、以下のような対策が考えられます。
- ●避難場所・避難経路をあらかじめ調べておく
- ●防災グッズ・非常食を準備しておく
- ●土嚢・止水板を備えておく
- ●水災補償を付けておく
万が一のため、普段からできる備えを実践していきましょう。
避難場所・避難経路をあらかじめ調べておく
万が一の事態に慌ててしまわないように、避難場所や自宅からの避難経路をあらかじめ調べて把握しておく必要があります。いつも家族全員が一緒に行動しているわけではないため、家族それぞれが水害の際に、どこへどのように避難すれば良いのか頭に入れておくことが重要です。
防災グッズ・非常食を準備しておく
災害時に備えて、普段から防災グッズや非常食を準備しておくと安心です。一般的には、非常用として最低でも3日分(9食分)の食料品備蓄が推奨されています。非常食は普段の食料品を多めに購入しておき、期限の古い順で消費していく循環型備蓄がおすすめです。
土嚢(どのう)・止水板を備えておく
建物の浸水被害を防ぐには、門や玄関などの開口部に土嚢・止水板を準備しておくと効果的です。住宅への水の流れ込みを防げれば被害を最小限に止められるため、復旧作業の時間や費用を抑えられるでしょう。
水災補償を付けておく
火災保険に加入する際は、上述した水災補償を付けておくと、万が一水害が発生した場合でも保険金を受け取れるため、元の生活に戻しやすくなります。注文住宅を建てる土地・地域の災害リスクを十分理解したうえで、保険料も考慮して補償内容を決めましょう。
水害に強い注文住宅をつくり家族で安心した暮らしを実現しよう
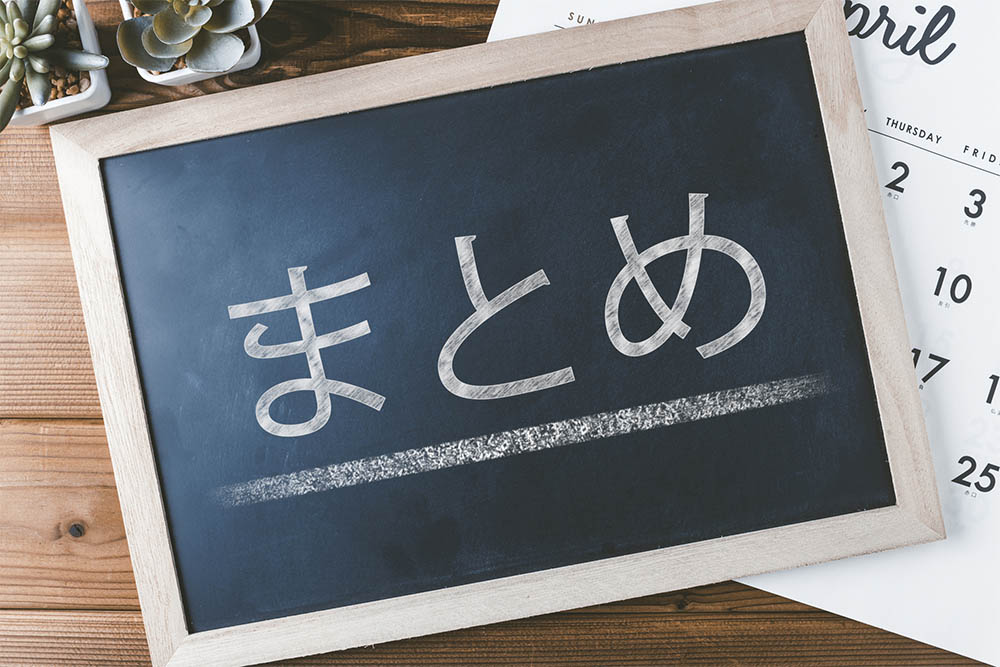
注文住宅で水害に遭うと、自宅に大きな被害をもたらし、修理や復旧にも多大な時間と費用がかかります。注文住宅を建てる際には地域や土地の水害リスクを把握するとともに、水害に強い家づくりのための対策を取り入れていきましょう。
ABCハウジングでは、関東・近畿地方を中心に、多くの総合住宅展示場を展開しています。ぜひお近くの住宅展示場へと足を運び、実際にモデルハウスを目で見て、手で触れて、水害に強い家づくりの実現に役立ててください。




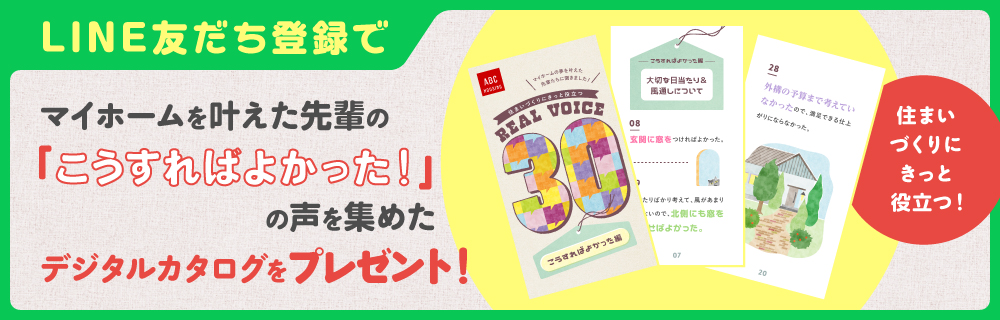
 前の記事
前の記事